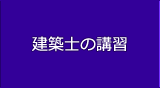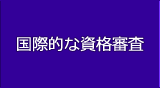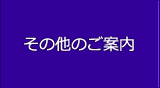『APECエンジニアStructural分野(建築構造)』の審査と継続職能開発(CPD)について
(財)建築技術教育普及センター企画部企画課副参事
佐藤景洋
「QUA クウェイ」NO.18(2001年)より
はじめに
APECエンジニア・プロジェクトに係る動きについては、予てからQUA CHANNEL等においてご紹介していますが、この度第1回目の審査申請書類の受付を昨年11月20日から12月20日まで1ヶ月間にわたり行い、現在すでに審査が始まっておりますので、その審査についてと、APECエンジニアになり得る要件のうち特に継続職能開発についてご紹介したいと思います。なお、今回の応募状況等については、「QUA18号」中の「QUA Information」にも掲載しておりますので、ご参照下さい。
1. APECエンジニアとは
1-1.APECエンジニアとは
APECエンジニア相互承認プロジェクトは、1995年に大阪で開催されたAPEC首脳会議において、技術者のAPEC域内流動化の促進が決議されたことを契機として、参加国間でプロジェクト開始のための準備が進められた結果、2000年11月1日以降プロジェクトが開始されるに至りました。
このプロジェクトの目的は、実務経験などについて一定レベル以上にあると認められる技術者に対し、APEC域内に共通の称号を与えることによって、これらの技術者の国際的な活躍を支援することです。
APECエンジニアとなるには、次に示す5つの要件について、自国の審査機関(各エコノミーに設立されるモニタリング委員会)の審査を受け、これに合格し、登録を受ける必要があります。
APECエンジニアとして登録を受けた技術者は、技術者としての能力がAPEC域内で実質的に同等であることが証明され、APEC域内に共通のAPECエンジニアという称号を受けたことになります。この段階で、APECエンジニアは、技術レベルの証明として、この称号を用いることが可能となります。
次に、相互承認の段階に移行することになりますが、これについては、今後、関係する二国間又は多国間の政府間での協議が整うことが必要です。この場合、協議の内容如何によっては、相互承認のための補足審査や追加的条件等が課せられる場合があります。
1-2.APECエンジニアの要件
APECエンジニアになるためには下記の5要件(APECエンジニアの5要件)を満たす必要があります。
(1) 認定又は承認されたエンジニアリング課程を修了していること、又はそれと同等の者と認められていること。
(2) 自己の判断で業務を遂行する能力があると当該エコノミーの機関で認められていること。
(3) エンジニアリング課程修了後、7年間以上の実務経験を有していること。
(4) 少なくとも2年間の重要なエンジニアリング業務の責任ある立場での経験を有していること。(この2年間は上記7年の内数としてもよい。)
(5) 継続的な専門能力開発を満足すべきレベルで実施していること。
さらに、次の2項目に同意しなければなりません。
- 自国及び業務を行う相手エコノミーの行動規範を遵守すること。
- 相手エコノミーの免許又は登録機関の要求事項及び法規制により、自己の行動について責任を負うこと。
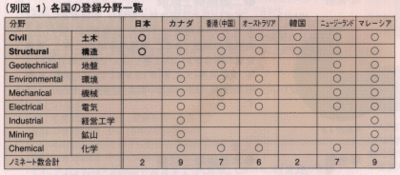
1-3.各エコノミーの分野登録状況
現在、APECエンジニアには、9つの専門分野があり、APECエンジニア・プロジェクトに参加している各エコノミーの分野登録の状況は別図1の通りです。
日本が登録しているのは、Civil Engineering(土木)とStructural Engineering(構造)の2分野です。
なお、分野の定義(対象範囲)については、各エコノミーによって若干の相違があります。
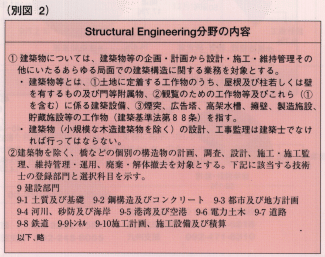
1-4.APECエンジニアと一級建築士
我が国においてAPECエンジニアで登録ができるのが、Civil Engineering(土木)とStructural Engineering(構造)の2分野であることは先述の通りで、対応する国内の資格者として技術士と一級建築士が挙げられます。
2分野のうちここで詳しく述べるStructural Engineering(構造)分野の定義は別図2の通りです。表中(1)に該当する部分が、建築構造分野となり、一級建築士のうち建築構造に関する実務を行う者(建築構造士など)が対象となります。(表中(2)は、技術士が対象となります。)
建築構造分野としての審査に合格した者は、Structural Engineering(構造)分野のAPECエンジニアとして申請により登録を受けることになります。
2.APECエンジニアの審査と登録
2-1.申請の概要
審査は、APECエンジニア・マニュアル(APECエンジニア調整委員会作成)及びAPECエンジニア審査説明書(日本APECエンジニアモニタリング委員会作成)に基づいて行われ、審査の合否に関する最終決定はモニタリング委員会が行うこととされています。
APECエンジニアのStructural(構造)分野のうち建築構造分野については、一級建築士のうち建築構造に関する実務を行う者(建築構造士など)が対象となりますが、これらのものに対する審査の実施に関する事務は、前述の審査説明書の基づき、モニタリング委員会からの委託を受けた建築エンジニア資格委員会(事務局:当センター)が行います。
2-2.審査のポイント
APECエンジニアになるためには、APECエンジニアの5要件を満たす必要があります。我が国において、建築構造分野に関するそれぞれの審査ポイントは、以下の通りです。
(1) 認定又は承認されたエンジニアリング課程を修了していること、又はそれと同等の者と認められていること。
(2) 自己の判断で業務を遂行する能力があると当該エコノミーの機関で認められていること。
- 一級建築士免許証の写しが添付されていることが確認される必要があります。
(3) エンジニアリング課程修了後、7年以上の実務経験を有していること。
- 建築構造に関する7年間以上の実務経験を有しているかどうかを審査します。
(4) 少なくとも2年間の重要なエンジニアリング業務の責任ある立場での経験を有していること。(この2年間は上記7年の内数としてもよい。)
- 下記に該当する建築構造に関する2年間の実務経験を有しているかどうかを審査します。
a. 比較的小さな規模の業務について、企画、計画、設計、管理、監理、調整などの大半を実施した経験を行い、業務を実施した経験。
b. 比較的規模の大きな業務の一部を担当して、業務全体を理解した上で関連部署との調整やチームの指導などを行い、業務を実施した経験。
c. 複雑な条件下の業務、新しい考え方が求められる業務、あるいは複雑な領域にまたがる業務などを実施した経験。
(5) 継続的な専門能力開発を満足すべきレベルで実施していること。
CPDについては、「3 継続的な専門能力開発(CPD)について」をご参照下さい。
2-3.審査方法
審査は書類審査と面接審査に別けて行われます。
書類審査については、申請者がAPECエンジニアの5要件を満たすかどうかについて、建築エンジニア資格委員会が当センターで受理した審査申請書をもとに行われます。
面接審査は、書類審査の結果、面接が必要とされた者に対してのみ行われます。面接審査は、一級建築士は原則として、建築構造士は書面のみによっては判断が困難な場合等に行います。
2-4.登録について
審査の合格者は、所定の期間内に登録手続きを行った後、モニタリング委員会で管理するAPECエンジニア登録者名簿に必要な事項が記載され、公表されます。
登録の有効期間は5年間で、更新の際は、登録有効期間満了前に、申請により「継続的な専門能力開発(CPD)を満足すべきレベルで実施していること」について審査を受けることとなります。
登録者は、
3.継続的な専門能力開発(CPD:Continuing Professional Development)について
(建築構造分野)
APECエンジニアの5要件の1つに『継続的な専門能力開発を満足すべきレベルで実施していること』があります。
「継続的な専門能力開発」とは、CPD(Continuing Professional Development)と呼ばれ、APECエンジニアとして必要な知識及び技能の維持向上に努めることが求められています。
3-1.CPDの目的
建築構造分野のAPECエンジニアとして求められるCPDは下記の事項に対応して、必要な知識・技能の維持・向上を行うことを目的としています。
- 技術の進歩・消費者ニーズの多様化・法令改正等社会状況の変化への対応
- 安全で良質な建築ストックの確保
- 信用の確保・増大
- 知識・技能の国際水準の確保 等
3-2.CPDとして修得すべき課題
建築構造分野のAPECエンジニアとして修得すべき課題は下記のように分類されます。
(1) 総合的なもの(安全、環境、倫理、契約等の他、経営・管理に関わるものを含む)
(2) 専門的なもの(建築構造に関する関係法令・技術・紛争事例等)
3-3.CPDの分類
建築構造分野のAPECエンジニアのCPDとしては、形態ごとに下表の(1)~(4)のように分類されます。
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| (1)参加(受講)学習型 | 提供されたプログラムを受講するもの |
| (2)情報提供型 | 研究成果など自らの知識・技能を他の建築構造技術者に提供・講義等するもの |
| (3)自己学習型 | 個人的に学習するもの |
| (4)実務学習型 | 建築構造に関する実務経験のうち、CPDとして効果が見込まれるもの |
3-4.CPDの要件
CPDの要件としての定められた時間数は、各々以下の通りとなります。
(1) 登録の更新に必要なCPD時間数
登録有効期間の5年間に250時間(目安として1年で50時間)
(2) 新規の場合の特例(当面)
審査申請時より過去約2年間に50時間(目安として1年で25時間)
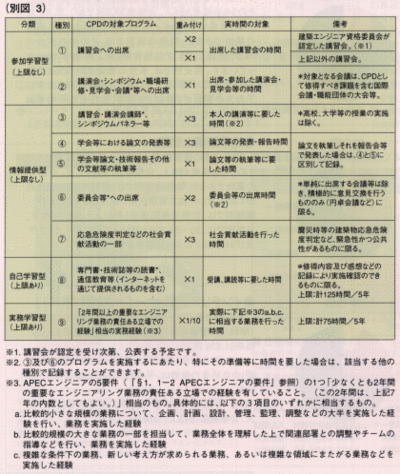
3-5.CPDの対象とCPD時間数
CPDの対象となる時間数は、実際に費やした時間数(実時間数)に、それぞれのCPDの対象となるプログラムに係る効果の程度を考慮した重み付けを乗じた時間数(CPD時間数)です。詳細については、別図3の通りです。
3-6.CPD時間数の上限
CPD時間数は、より幅広い知識の習得・維持向上を目指したCPDの実施を促すために、自己学習型及び実務学習型のプログラムについて上限値を定めています。
なお、新規登録者の場合は、当面の経過措置として過去2年間の時間数の要件を更新の場合の半分としている関係上、上限値も、1年あたりで各々更新の場合の半分の時間となります。上限値は下表の通りです。
| 分類 | 更新 | 新規登録 |
|---|---|---|
| 自己学習型 | 125時間/5年(目安として1年で25時間) | 25時間/2年(目安として1年で12.5時間) |
| 実務学習型 | 75時間/5年(目安として1年で15時間) | 15時間/2年(目安として1年で7.5時間) |
3-7.CPDの記録と保管
審査の過程でCPDの実施を証明する書類の提出を求める場合がありますので、講習会受講証、シンポジウム参加証や論文の写し等は、保管しておく必要があります。
APECエンジニアとして登録を受けた後も、登録更新の際にも、審査申請書の様式4(CPDに関する記録)を提出することになりますので、普段からCPD記録をとっておくことが重要になります。
4.監査・制裁措置等
モニタリング委員会及び建築エンジニア資格委員会では、APECエンジニアに対し、一定期間ごとに、一定程度の数を抽出し、監査を行うことがあります。
なお、虚偽の記載等が発覚した場合には、登録の抹消等の制裁的措置が行われます。
おわりに
APECエンジニアについては今後、2国間での政府間協議等にステージを移していくことになります。
また、今回特に取り上げた「継続職能開発(CPD)」は、今まであまり馴染みのないものであったかもしれません。しかし、これからは資格の国際認証などを考えるときに、一度その資格を得た者(エンジニアなど)が、少なくともそのレベルを維持し、さらに時代の変化(技術的に、法律的になど)に対応できているかを推し量る一つの手だてとして取り上げられるのは必至だと考えられます。
現在、建築士については、建築士法22条において、その「知識及び技能の維持向上に努めなければならない」と記載されているだけに過ぎませんが、皆さんもこの機会にそのあり方について考えてみてはいかがでしょうか。