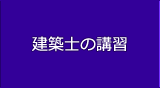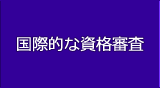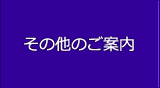フランスのアーキテクト制度
建築技術者教育研究所 所長/小泉重信
フランスは、シラク大統領が保守政権に返り咲いて半年が経過しましたが、国際的には核実験の再開による批判、国内的には、厳しい財政赤字・失業の増大、テロの多発、社会保障制度改革反対のゼネスト等多難な事件が相次いでいます。
しかし、文化の伝統、都市景観の歴史等については、ヨーロッパの先達としての自負を持ち続けているといえます。
いわゆるプロフェッションとしてのアーキテクトの歴史は、世界で最も古典的な伝統を受け継ぎ現代に至っています。
今回は、フランスにおけるアーキテクトの制度を取り上げ紹介します。
「建築 普及&資格」NO.6(1996年)より
1 建築法と建築家登録制度
フランスに限らず、欧米のほとんどの国においてはアーキテクト(以下、建築家と訳す)とビルディングエンジニア(いわゆる建築技術者)とは、教育の体系、資格制度、職能団体構成等、すべての点で明確に区別され、わが国のような、広範囲な分野の人を含む建築士とは単純に比較できないことを先ず承知しておく必要があります。建築家は決して技術者とはいわないのです。
さて、フランスの建築に関する現在の諸制度は、1977年1月3日公布の「建築法」に基づいております。冒頭の第1条には、建築は文化の一表現であることを高らかに謳っております。わが国の建築基準法が技術的な最低限の基準を遵守させようとしているのとは、性格が大いに異なっていることがわかります。
建築法は6章からなり、1.建築家の関与、2.建築・都市計画・環境審査会、3.建築家の専門職能業務、4.建築家の職能組織、5.都市計画法典の改正・補足、6.その他経過措置となっております。第1章第3条では、建築許可の対象となる工事については、建築計画に建築家の関与を義務化しています。即ち責任者として建築家の関与が必要であるとされていますが、他の人が設計してはいけないとはなっていません。つまり設計の業務独占とは若干意味が異なります。また、政令により、非農業建築物については170平方メートル以下、農業建築物については800平方メートル以下の建築物では、建築家の関与義務は免除されています。
1977年法が制定される以前では、1940年法で建築家は称号の独占だけが認められていましたが、1977年法で称号の独占と建築家の業務関与が義務化されましたので、規制は強化されたことになります。
建築法に基づく建築家には次の三種が含まれています。いわゆる自然人としての建築家、建設法人、法施行時に経過的措置によって認定建築技師として建築家協会に登録された者の三種です。
1993年末現在、第一の建築家で建築家協会に登録されている人は、26,280人、このうち首都圏に相当する、イル・ド・フランス地方に、9,725人、パリ市には5,187人の建築家がいます。イル・ド・フランス地方には、全国の36%が集中していることになります。
1986年末現在では、建築家数は全国で23,143人であったので、7年間で13.6%増、年平均僅か448人しか増加していないことになります。
建築専門学位を持った有資格者は、35,000人いるといわれていますので、建築家の登録率は約75%となります。
2 建築専門教育制度
1671年、フランスは王立アカデミーの一つとして建築アカデミーを創設し、その付属学校としてヨーロッパ最初の建築家養成のための教育機関を設立しました。その後1819年、建築と絵画・彫刻の学校が統合され、総合的な芸術家養成機関としての国立美術学校(エコール・デ・ボザール)は、約150年にわたってフランスの建築家を輩出してきたのです。
1968年、世界の大学紛争のきっかけともなったいわゆる5月革命が起こり、フランスの高等教育に大変革が引き起こされました。1968年11月制定された「高等教育基本法」はその目標として知識の伝達、研究の促進、人間の教育の3つを掲げ、特に最後の人間の教育については、人間がより良く自らの運命を制御できるようにすることを狙っています。そして芸術と文学を科学と技術とに結びつけるような大学を構成するよう再編されました。エコール・デ・ボザールも22校の国立建築学校に解体され、アトリエ制の廃止、教育課程は6年制とされました。1970年代の終わりに、建築教育の管轄は文化省から施設・運輸・観光省に所管換えされ、1984年には教育年数は5年に短縮されました。しかし、学生が実際に卒業できるのには7年ぐらいかかっているといわれています。
フランスでの建築家資格を得る通常の方法は、これら国立建築学校22校の学位(政府認定学位でDPLGという)、ストラスブルグ国立芸術工科高等学校(ENSAIS)の学位、または私立建築高等学校(ESA)の学位(DESA)を有していなければなりません。これらの学位を有している人は約37,000人いるといわれています。
3 建築家協会(OA)
建築家協会は1940年の旧建築家法により設立され、1977年の建築法にも引き継がれた組織です。フランスにおいて建築設計業務を営もうとする個人及び組織に対し、この建築家協会の地方評議会に登録することを要求しています。登録すると会員は建築家または建築設計会社の資格を得ることになります。
建築家協会は26の地域評議会からなり、フランス本土に22、海外領土に4つあります。地方評議会の評議員は、所属する登録建築家全員による選挙で、登録されている建築家の数に応じ8名から24名が選ばれます。地方評議員の投票により全国評議会の評議員が24名選出されます。全国と地方の兼任はできないこととなっていますが、全国評議員に立候補するには地方評議員を一期以上務めていなければなりません。
建築家協会の地方評議会の任務は、建築家登録の管理を行うこととされ、全国評議会の任務は、地方評議会の活動の調整、情報交流、建築家業務及び建築教育組織等、行政からのあらゆる諮問に対して意見を表明することです。共に建築家の資格保護や権利義務に対する適正な活動を行うこととされています。
建築家協会は、文化担当大臣の監督下に置かれており、大臣は、政府委員を任命し、大臣の代理としての政府委員は、評議会のメンバーとして参加することとなっています。現在は、土地整備・施設・運輸省の管轄になっています。
職能団体としての建築家協会の課題の一つに教育があります。それは専門教育としての学校教育と生涯教育的な継続職能研修の実施です。評議会としても建築担当行政局と、建築専門学校と定期的に関係を持ってプライオリティの高い改革に努めています。
継続研修地方代表団(DRFC)は評議会に特別な活動としてセミナーを開催させています。
4 就業形態
個人としての建築家の職能構成を見ると、1993年末で、個人自由業72%、パートナー共同経営12%、公務員3%、被雇用者9%、教育・その他4%となっています。最近の傾向としては、自由業としての個人が減少し、パートナー共同または法人形態がやや増加しているようです。
建築家事務所の規模は、フランスでは一般に小さく、30人以上の建築家を抱えている事務所でさえ、ほんの一握りしかないようです。建築家事務所の大半は1人ないし3人の建築家で運営されています。
建築業務を行う組織の形態については、1977年の建築法及び1985年の法律等で次の3つが認められ、各々特徴があります。
1.個人自由業・・・・・・完全な管理権、資本提供不要、責任は無限
2.職能民事会社(SCP)・・・・・・パートナーシップ、独立性保持、少資本、共同及び個々の責任
3.商事会社
(1)有限責任個人企業(EURL)・・・・・・1人または複数の建築家で設立、資本金内の責任、社会保険と税減免、最低5万フランの資本金必要
(2)有限責任会社(SARL)・・・・・・最低2人以上のパートナーで設立、資本金内の有限責任、パートナー雇用可能で社会保険や税法上従業員として扱える、資本金5万フラン以上、会計監査報告必要
(3)株式会社(SA)・・・・・・株主7人以上、その内の2人は株式50%以上を所有する建築家で、1人が50%を超してはならない。最低25万フラン以上の資本金必要、設立手続に時間と費用がかかる。会計監査報告必要
1989年当時、登録建築家のうち1,400人が上述した企業に就職しており、その構成は、SCP54%、EURL6%、SARL34%、SA4%、その他2%となっており、最近SARLが急速に伸びているといわれています。建築家による企業家的アプローチがとられ始めていることを表しているようです。
| 日本 | フランス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国土 人口(1991年) 1人当りGDP(1993年) |
378千平方キロメートル 12,392万人 33,903ドル |
552千平方キロメートル 5,705万人 21,818ドル |
||||
| 住宅建築 (1994年) |
着工戸数(千戸) | 構成比(%) | 人口千人当たり(戸数) | 許可戸数(千戸) | 構成比(%) | 人口千人当たり(戸数) |
| 合計 一般住宅 個人住宅 集合住宅 共同施設 |
1570.3 1570.3 728.0 842.3 - |
100.0 100.0 46.4 53.6 - |
12.7 12.7 5.9 6.8 - |
360.5 356.1 165.5 190.7 4.3 |
100.0 98.8 45.9 52.9 1.2 |
6.3 6.2 2.9 3.3 0.1 |
| 非住宅建築(1994年) | 着工面積(千平方メートル) | 構成比(%) | 人口千人当たり(平方メートル) | 許可面積(千平方メートル) | 構成比(%) | 人口千人当たり(平方メートル) |
| 合計 事務所 店舗 工場・作業場 倉庫 教育 医療 その他 |
81,267 11,337 10,915 13,317 10,562 5,630 2,937 26,749 |
100.0 14.0 13.4 16.4 13.0 6.9 3.6 32.9 |
656 91 88 107 85 45 24 216 |
34,560 5,645 2,931 4,433 4,171 2,341 2,203 12,837 |
100.0 16.3 8.5 12.8 12.1 6.8 6.4 37.1 |
606 99 51 78 73 41 39 225 |
| 建築家(1994年初) | 一級建築士 250,688人 うち設計担当(推計)* 93,500人 |
人口1万人当り(人) 20.2 7.5 |
アーキテクト 26,280人 |
人口1万人当り(人) 4.6 |
||
*日本の設計担当一級建築士数は、(社)日本建築士会連合会の実態調査の結果による生存率97.4%、建築設計業務従事率38.3%を利用して推計したもの。
5 職能倫理綱領と懲戒
フランスの建築家に対する称号保護と建築設計への関与特権を与えた代償として、職能活動に対する義務綱領を制定し、建築家懲戒裁判所を設置し綱紀の維持に務めることが法定されています。
建築家の義務としては、保険加入の義務、委託された建築計画の申告義務、地方評議会への届出義務、倫理綱領の遵守義務等です。
倫理綱領は1980年3月の政令により、47条にわたる義務規定が比較的詳細に規定されています。特に、種類の異なる他の職業を兼任している時は、その業務と完全に独立させ、しかも相手側に公知事実となるようにしなければなりません。当然、設計の名義貸しや下請への発注は禁止されており、同業者への信義や名誉を尊んでいます。
懲戒裁判の手続きもかなり詳細に規定されており、特徴的な点は、処分の決定を行政機関と独立した第三者機関が相当していることです。
6 責任と保険
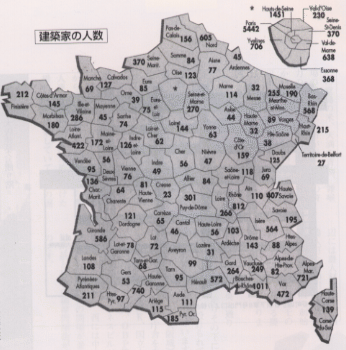
建築工事保証保険制度は、かねてからありましたが、建築工事の事故は、多様、多額であり保険効力が発効するまでに長期間を要します。1978年スピネッタ法と通称される建築責任保険法が制定され、建築家、技術事務所、施工業者、プロモーター、建築材料メーカー、輸入業者、さらには建築主まで強制的に保険に入る義務が生じました。保証期間10年間の規定も、他国には見られない長期のものです。
契約上の責任は、工事が構想された時点から、実際に完成された時点を超え、最長で30年に及ぶ場合もありうるそうです。
元来、10年間責任は、ナポレオンの民法典にまでさかのぼるものです。
この他に現場単独保険(PUC)といわれる建設関係者全員に対する10年間責任の補填を行うものがあり、コスト削減を可能にしていますが、第三者に対する民事責任は補填の対象にならない短所があります。PUCの費用は建築費用の2ないし3%です。フランスの建設業全体で保険に費やしている費用の総建設費に対する比率は3%から8%に達すると推定されています。
建築家は、既に1937年に自らの保険に対するニーズに対処するためフランス建築家相互保険会社(MAF)を設立し、現在は登録建築家の90%が利用しています。提供している保険は「建築家職業責任保証契約」と呼ばれ、損害賠償訴訟一件当たり、最高2,000万フランです。これは建築家の責任部分のみに対し補填するものです。
MAFの標準保険料は、建築家の役割が完全任務(M1)の場合、建築費の0.0455%で、最低金額は455フランです。保険料はプロジェクト毎に計算されますが、支払いは年単位でなされ、保険料の平均は建築家の手数料の8%から15%になっています。
7 コンクールと設計報酬
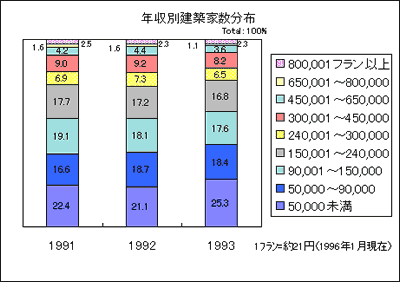
フランスにおいては一定額以上の中央政府の仕事はすべて設計競技に付されなければならないことになっており、建築家、特に若い人にとって仕事を獲得するのにコンクールは重要なチャンスとなっています。建築家及び事務所の評判を高めるためにも権威あるプロジェクトに応募することは大切で、民間市場に入る際の営業手段としてもコンクールの成果は利用されています。
建築家の設計料率については、1980年以降民間はもとより原則として契約当事者での自由な交渉に任されることになりました。
しかし中央政府の契約については、1973年2月の政令で、建築物の用途、複雑性(10ランク)及び工事金額による標準料率が定められています。4.3%から最高20.6%までとなっていますが、一般には8%から12%の間です。地方自治体や公的機関は、特段の取決めはありませんが、国の料率を準用しているようです。
建築活動は、長く不況が続き建築家も厳しい状況が続いていました。1993年、建築家の78%は年収が24万フラン以下であったと建築家協会は発表しました。つまり4分の3が約500万円以下ということです。建築家は活動の範囲を拡げたり、法人ではリストラに努力しているようです。従来やらなかった設計分野への参加、小規模コンクールへの応募、海外市場への参入、業務のコンピュータ化等に真剣に取り組み始めているようです。