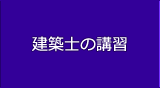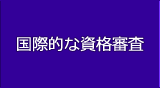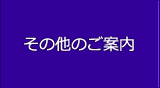欧州連合の建築家資格相互承認制度
建築技術者教育研究所主任研究員/池田吉朗
1993年1月、ECが8年越しで進めてきた市場統合がついに実現し、EC内における人、物、資本、サービスの自由移動が保障されることとなりました。
さらに、同年11月には欧州連合条約(マーストリヒト条約)が正式に発効し、欧州連合(EU)が発足しました。
これにより、加盟12ヵ国の国境が消滅し、約3億4千万の人口を有する巨大な一国家が誕生したといえます。
この連載では、「諸外国における建築技術者制度の現状」をテーマに、建築に関わる諸制度を紹介して行く予定です。
第1回目の今号では、欧州連合における人の自由移動の一環として実現した「建築家資格の相互承認制度」を取り上げます。
(※本文は、欧州共同体(EC)と称した時期の内容のため、EUではなくECで統一しました。)
「建築 普及&資格」 創刊号(1994年11月1日)より
1 理事会指令(85/384/EEC)の概要
建築家資格の相互承認制度の基になっているのは、ECの閣僚理事会が1985年に出した指令(85/384/EEC)です。この指令は加盟各国に出されたもので、各国は指令に従ってそれぞれの国内法(例えば、イギリスでは建築家登録法、ドイツでは各州の建築家法)に必要な改正を行っています。
この指令は、1967年5月にEC委員会から閣僚理事会に対して行われた提案に端を発していますが、この理事会で合意が得られるまでに18年もの長い年月を要したことになります。その原因としては、検討期間中に加盟国がしだいに増加したために検討が後戻りしたこと、各国ごとに建築家制度にかなりの違いがあったこと、自国の教育課程を承認の対象とするよう各国からさまざまな要望が出されたこと、他の重要な案件の後回しになったことなどがあげられます。
EC各国の建築家制度は、表1のとおりですが、アイルランドとデンマークには建築家の登録制度についての法律がなく、オランダも法律が制定されたのは、閣僚理事会指令が出された後の1987年7月のことです。また、オランダとイギリスでは、建築家の登録制度はあるものの、建築家による設計業務の独占は規定されていません。
| 法律上の保護(A) | 建築家の人数(B) | |||
|---|---|---|---|---|
| 称号の独占 | 業務の独占 | 登録建築家の人数 | 人口1,000人当たりの建築家の人数 | |
| ドイツ | あり(州法) | あり(州法) | 73,500 | 0.95 |
| フランス | あり | あり | 25,600 | 0.44 |
| イタリア | あり | あり | 52,175 | 0.96 |
| オランダ | あり | なし | 4,000 | 0.27 |
| ベルギー | あり | あり | 8,500 | 0.86 |
| ルクセンブルク | あり | あり | 200 | 0.53 |
| イギリス | あり | なし | 30,200 | 0.54 |
| アイルランド | - | - | 1,200 | 0.34 |
| デンマーク | - | - | 5,940 | 1.17 |
| ギリシャ | あり | あり | 12,000 | 1.19 |
| スペイン | あり | あり | 19,000 | 0.49 |
| ポルトガル | あり | あり | 4,500 | 0.41 |
出典:
A欄 RIBA Journal,August 1993,P12
B欄 Architectural Practice in Europe,Italy編、P80(1992年、RIBA発行)
1967年当時のEC加盟国はフランス、西ドイツ、イタリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブルクの6ヵ国でしたが、1973年にイギリス、アイルランド、デンマークが、1981年にはギリシャが加盟しました。そして理事会指令後の1986年にスペインとポルトガルが加盟し、現在の加盟国は12ヵ国です。さらに、来年1月にはオーストリア、ノルウェー、スウェーデン、フィンランドの4ヵ国が新たに加盟する見通しとなっています。
2 理事会指令の内容
指令の対象
この指令は、各国ごとに「アーキテクト(建築家)」という称号の下で通常従事する活動に適用されるもので、建築家の活動範囲を全加盟国で統一しようとするものではありません。これは建築家教育の最低年限を規定し、建築家の登録制、称号独占が実施されている場合について、その相互承認を促進することを意図したものです。ですから国によっては、国内法上でエンジニアなども建築設計を行える場合がありますが、それに関してこの指令は適用されません。
この指令は、加盟国に対し、4年制大学の水準以上という要件を満たす教育・訓練の修了により得られた他国での卒業証書(ディプロマ)等の公的な資格証拠を持つ者と、自国内で授与された資格証拠を持つ者とを同等に扱って建築家登録を行うよう求めています。
このように、教育・訓練の期間については4年間という基準が設けられましたが、実務経験その他の要件についてはの基準は設定されていません。各国は、建築家登録のために従来どおり実務経験その他の要件を課すことができますが、他の加盟国で行った実務経験あるいは破産宣告を受けていない旨の証明書を受け入れるなど、他国からの申請者に対して便宜を図ることが求められています。
事例として、ドイツのバイエルン州の建築家法「第4条 登録のための前提条件」の改正内容を簡単に示します。(第2項第2文の太字が追加された部分です。)
第4条 登録のための前提条件
(1)建築家名簿に登録申請することができるのは、その居住地又は開業地を州内に有する以下の者である:
1 建築学に関して、ドイツの大学又は同等な教育機関を卒業し、かつ、
2 少なくとも3年間、実務活動を終えた者。
(2)前項第1号の前提条件は、外国高等教育機関で同等な修了試験に合格した者によっても満たされる。EC加盟国の国籍を有する者の場合、EC理事会指令85/384/EECにより告示された卒業証書等も同等と見なされる。
教育・訓練の資格証拠の要件
各加盟国で承認される公的な資格としては、大学もしくは同等の機関における最低4年間の全日制の教育・訓練、または、6年間のうち最低3年間全日制の大学もしくは同等の機関で学ぶ課程と定めています。これらには、学位レベルの試験合格またはそれと同等の内容の取得が伴わなければなりません。課程の内容については詳細な最低基準に代わり、理論的及び実務的側面の間でバランスがとれるように意図された、11項目にわたる指針が定められています。
また、各国別の承認された課程のリストでは、通常の建築の課程のほか、ギリシャの項には、建築分野での活動を認められた土木工学の卒業証書も含まれる一方、ドイツについては大学のほかに、3年制の専門単科大学(Fachhochschule)も、4年間の実務訓練で補足されるならば承認されることが規定されています。
建築家分野における顕著な業績によって、建築家の称号を授与することができるという制度を持つ国もあり、その証明書も他の加盟国で承認されます。さらに、指令の発行日以前に所定の教育要件を満たしていないにもかかわらず、建築家の称号を使用することが認められていた者に対しての救済措置等も設けられています。
実務経験の要件
以上の規定は学校教育面での要件を主体としたものですが、建築家という称号の使用及び建築家の業務の従事のために実務経験の要件を課している国もあります。その場合、外国での資格取得者は受入れ国での実務経験の要件を満たさなければなりません。
例えば、実務経験の必要がないオランダでは、4年制の建築教育を受けた者は卒業後すぐに国内で建築家の登録をすることができます。しかし、その者が5年間の教育及び2年間の実務経験を必要とするイギリスで建築家として登録する場合には、指令に基づき、教育は4年間のまま承認されますが、2年間の実務経験が必要となってきます。その実務経験については、イギリスで得たものでなくても差し支えありません。
開業、サービス提供の促進
自国で建築家として開業する場合でも資格の一部として、品格が良好であることを示す人物証明書、破産宣告されていないという証明書、職能賠償保険による担保の証拠を要求する国があります。
そのような国では、申請する場合は申請者は出身国で発行された証明書を提出しなければなりません。また、申請者の出身国(またはそれまで業務を行っていた国)は受入れ国に対して、当該者の職能上もしくは行政上の懲戒処分やその他の犯罪による罰則に関するすべての情報を送付する義務があります。
諮問委員会
EC委員会の中に、「建築分野における教育・訓練に関する諮問委員会」が設置されています。この諮問委員会は、加盟国ごとに所管官庁、職能団体及び教育機関の代表である委員3名、合計36名で構成されています。
諮問委員会で、各加盟国から通知された新しいディプロマ等の資格証拠が要件に該当するかどうかを審査しますが、最終決定はEC委員会が行います。
3 指令をめぐる状況
この指令では、公布から2年後の1987年6月までに各国が国内法の整備を行うように規定しています。これによりオランダで新法が制定されるなど、9ヵ国で国内法の整備が行われましたが、ギリシャではまだ行われておらず、アイルランドとデンマークでは法律に基づく登録制がないままです。(1993年秋現在)
また、先に述べた諮問委員会は、教育・訓練に関して指令の条項の修正勧告を行うことができます。1990年3月の勧告では、「大学等における教育・訓練期間を5年以上とし、さらに実務経験を2年間設けるべきである、教育・訓練の期間が6年間でその中に実務経験の1年間が含まれている場合は、さらに実務経験を1年間だけ設ければよい」ということを述べています。
今まで述べてきたEC理事会に従って、各国が必要な国内法整備を行い、他国での資格取得者を受け入れているわけです。一部の国についてはその人数が分かっていますので、表2に示します。4ヵ国のデータですが、表1と併せて検討すると、各国とも、0.7~1.2%程度の建築家がこの制度によって登録されているようです。
この制度についての王立英国建築家協会(RIBA)及びドイツ建築家協会(BDA)の担当者の意見を聞くと、概ね高く評価しているようです。ただ両協会とも会員の資格要件を高く狭く設定しているため、外国での資格取得者がイギリスまたはドイツで登録を認められても、それだけでは協会の会員になれない場合が多いそうです。また、資格制度以外にも、言語、会社法、建設の方法などに国ごとの違いがあり、他国での業務への参入が難しいのが現実です。さらに、ドイツ建築家協会では、各国の文化、仕事のやり方を無視した統一化の傾向は好ましくないという意見もありました。
| 受入れ国 | フランス | オランダ | ベルギー | 英国 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 開業を認められた総数 | 177 | 48 | 93 | 258 | |
| 国籍別 | ドイツ | 20 | 12 | 2 | 35 |
| フランス | 0 | 0 | 19 | 9 | |
| イタリア | 37 | 0 | 10 | 17 | |
| オランダ | 3 | 27 | 45 | 17 | |
| ベルギー | 35 | 3 | 3 | 8 | |
| ルクセンブルク | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| イギリス | 45 | 4 | 2 | 11 | |
| アイルランド | 8 | 0 | 0 | 124 | |
| デンマーク | 4 | 0 | 1 | 16 | |
| ギリシャ | 7 | 1 | 7 | 20 | |
| スペイン | 9 | 1 | 1 | 0 | |
| ポルトガル | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 資格取得国別 | ドイツ | 18 | 25 | 3 | 37 |
| フランス | - | 2 | 18 | 10 | |
| イタリア | 32 | 1 | 10 | 16 | |
| オランダ | 3 | - | 48 | 17 | |
| ベルギー | 33 | 5 | - | 8 | |
| ルクセンブルク | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| イギリス | 44 | 7 | 2 | - | |
| アイルランド | 8 | 1 | 0 | 130 | |
| デンマーク | 4 | 5 | 1 | 16 | |
| ギリシャ | 4 | 0 | 7 | 22 | |
| スペイン | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 | 1 | |
出典:EC委員会より入手した資料