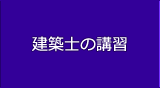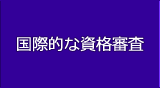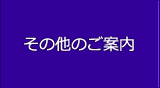アメリカ合衆国におけるコンピュータ化された建築家登録試験について
「QUA クウェイ」NO.4(1997年)より

NCARB本部(ワシントンD.C.)
前号『QUA』(No.3)でお知らせしたとおり、1997年3月24日から26日の3日間、当センターの片山正夫理事長を代表とする6名の調査団が、ワシントン特別区にあるアメリカの建築家の試験・登録機関であるNCARB(National Council of Architectural Registration Boards 全米建築家登録委員会協議会)本部ほかを訪れ、1997年2月よりコンピュータによる試験に切り替えられたアメリカの統一的な建築家登録試験ARE(Architect Registration Examination)について調査を行いました。アメリカでは既に、看護婦、パイロット、大学卒業資格試験など多くの資格試験がコンピュータ化されていますが、いずれも多肢択一式の出題をコンピュータ化したものです。今回コンピュータ化されたAREは、多肢択一式の科目の他、設計製図の試験まで専用のCADソフトを開発して出題から採点まで全てをコンピュータ化したものです。ここでは、そのコンピュータ化された試験システムについて、NCARB『建築家登録試験案内書』(1997年版)等を基にご紹介いたします。
1 ARE(建築家登録試験)とは
アメリカで建築家の資格を得るためには、NCARB加盟委員会(全米50州、コロンビア特別区、グアム、北マリアナ諸島、プエルトリコ、米領バージニア諸島の建築家登録委員会で構成)の一つに建築家登録を申請し、登録が認められなければなりません。登録されるには、建築教育(大学の建築学科を卒業等)、建築実務(大部分の州が、建築教育を受けた後3年間の実務訓練を義務付けている。)、建築家登録試験に合格の三つの条件を証明することが必要となります。
AREは、この建築家登録試験であり、NCARBとカナダ建築評議会委員会(CCAC)が共同で開発したものです。(カナダの各州でも使用されている。)この試験では、建築全部門の能力を備えているかどうかを調べるのではなく、公衆衛生、安全性、福祉に最も影響を与える業務のみをカバーすることを目的としています。試験問題は、建築実務を指向したもので、建築家が提供する一般業務のモデルに基づいています。
試験科目は、9科目あり、うち6科目(1.事前設計、2.一般構造、3.横力、4.機械・電気システム、5.材料・工法、6.工事書類・業務)が多肢(4肢)択一式の試験で、3科目(1.敷地計画、2.建築計画、3.建築技術)がビネット(vignette:もともとはフランス語で小さな物語の意、ここでは試験の小課題をさしている。)とよばれる設計製図の試験で構成されています。いずれもコンピュータを使った試験となっています。

試験センターのある建物(ワシントンD.C.)
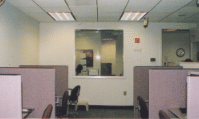
試験会場
2 いつでも、どこでも受験が可能
登録を希望する各州の建築委員会から受験許可証が得られた受験希望者は、希望する試験センター(米国、その統治領およびカナダ全土で計約220箇所あり、登録希望地域と同一地域の試験センターでなくてもよい。試験センターではAREだけでなく、他の資格試験等も同時に行われる。)に電話で受験予約を行い(直接出向いてもよい。)、センターの営業日であればいつでも受験することができます。
受験予約は、センターの営業日(一般には月曜から金曜)で受験を希望する日の9ヶ月以内で72時間以上前であれば、先着順に各試験センターの席数分(通常5~15席、最大はニューヨークの45席)だけ受け付けます。
受験料は、1科目当たり$79~$155、9科目合計$980であり、支払方法は、クレジットカード、小切手または送金為替のいずれかを選択できます。
予約のキャンセル、試験場所・試験時間の変更は、予約日の2営業日前の正午までに試験センターに電話連絡をすれば行うことができます。なお、試験センターは、シルバン・プロメトリック社という民間企業です。
3 試験の実施方法
試験センターでは、受験者の受験科目に応じて出題する問題を試験日の前日の夜に中央の大型コンピュータから試験センターのサーバーにダウンロードします。各試験センターは、NCARBが定める次のような標準試験基準にしたがって試験を運営しています。
- 受験者には、署名のある2種類の身分証明書(1種類は写真のあるもの)の呈示を求める。
- 試験センターでは、受験者に署名を求めるとともに、受験者の顔写真を撮影し、試験結果報告書に貼付する。
- 試験実施時には受験者の様子を監視(試験係官による監視、試験会場の録画、録音)する。
- 受験者は、試験センターに苦情がある場合は、直ちに書面またはFAXでNCARBへ連絡することができる。(このときは、試験会場の録画・録音のテープを再生して苦情に対応するとのことです。)
4 試験の構成・試験時間
(1)多肢択一式試験
表-1に示すように、6科目とも最高4群の問題が出題されます。第1群では、横力が40問、その他の科目が各々65問です。(このうち一部の問題各科目とも15問は、採点されずに将来の試験問題のためのデータとされます。受験者にそのことはあらかじめ知らされていますがどの問題がそれに該当するかはわからない。)その問題群の中であれば解答を見直し変更できます。コンピュータの画面には残りの試験時間、今何問目かが表示されます。また後で再確認したい問題にはマークを付けておくことができますし、解答一覧も見ることができます。
第1群が終わりますと自動的に採点が行われ、その科目の合格、不合格、合否確定不可の三つの判定がされます。判定が合格または不合格であれば、そこで試験が終了します。合否確定不可の場合は、第2群の問題25問(横力は15問)が出題されます。第2群が終わりますと、第1群および第2群を合わせた成績により合否が判定されます。
第2群でも判定できない場合は、第3群の問題へ、さらに判定できない場合は最終の第4群の問題を受け、その後合否が決定します。このように第4群まで受けた場合は、横力が85問、その他の科目が各々140問出題されることになります。
したがって、試験の成績次第によって受ける問題数および試験時間が変わってきます。所要時間には、一般的指示説明、コンピュータの指導プログラムによる個人指導、試験終了後のアンケートの時間が含まれます。
| 試験科目 | 第1群 | 第2~4群 | 計(第1~4群) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 問題数 | 制限時間 | 問題数 | 制限時間 | 問題数 | 所要時間 | |
| 事前設計 | 65問 | 99分 | 各25問 | 各37分 | 計140問 | 4時間 |
| 一般構造 | 65問 | 114分 | 各25問 | 各42分 | 計140問 | 4.5時間 |
| 横力 | 40問 | 72分 | 各15問 | 各26分 | 計85問 | 3時間 |
| 機械・電気システム | 65問 | 84分 | 各25問 | 各32分 | 計140問 | 3.5時間 |
| 材料・工法 | 65問 | 84分 | 各25問 | 各32分 | 計140問 | 3.5時間 |
| 工事書類・業務 | 65問 | 99分 | 各25問 | 各37分 | 計140問 | 4時間 |
(2)設計製図試験
表-2に示すように、3科目15ビネット(小課題)で構成されています。各科目は、いくつかのビネットで構成される2~3のセクションに分かれています。セクション内でのビネットの解答順序は自由で、各ビネットの解答時間には制限がありません。また、セクション内でのビネットの見直しも可能です。ただし、セクションの制限時間が切れたり、終了すると、そのセクションのビネットに戻ることはできません。
セクションごとに制限時間および強制的な休憩時間が定められています。また、所要時間には、一般的指示説明、コンピュータの指導プログラムによる個人指導、試験終了後のアンケートの時間が含まれます。
| 試験科目 | セクション | ビネット | 時間配分 | 制限時間 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敷地計画 | 第1セクション | 敷地デザイン | 60分 | 2時間 | 5時間 |
| 敷地ゾーニング | 30分 | ||||
| 敷地パーキング | 30分 | ||||
| 強制休憩 | 15分 | ||||
| 第2セクション | 敷地分析 | 30分 | 1時間30分 | ||
| 敷地断面 | 30分 | ||||
| 敷地グレーディング | 30分 | ||||
| 建築計画 | 第1セクション | ブロックダイアグラム | 60分 | 1時間45分 | 7時間30分 |
| インテリアレイアウト | 45分 | ||||
| 強制休憩 | 30分 | ||||
| 第2セクション | 基本設計 | 4時間 | 4時間 | ||
| 建築技術 | 第1セクション | 建物断面 | 60分 | 1時間45分 | 7時間 |
| 構造レイアウト | 45分 | ||||
| 強制休憩 | 20分 | ||||
| 第2セクション | アクセス方法-傾斜路 | 45分 | 1時間45分 | ||
| 機械・電気設備計画 | 60分 | ||||
| 任意休憩 | 5分 | ||||
| 第3セクション | 階段設計 | 60分 | 1時間45分 | ||
| 屋根伏図 | 45分 |
(3)練習プログラム
設計製図を受験する場合は、試験日当日、プログラムによる個人指導がありますが、受験する前にあらかじめ無料のCD-ROM等の練習用プログラムのコピーを取り寄せることが可能です。また、試験センターで有料制の練習プログラムを使用することができます(1時間当たり$12)。
(4)単位の選択
設計製図の試験では、メートル法かフィート・インチ法を選択します。選択を確定するとその科目については変更することができません。
5 試験の採点・合格基準
全科目ともコンピュータにより採点されます。
(1)多肢択一式試験の採点
合否は、受験者の成績が初級レベルの能力に相当する設定合格点以上であるか否かによってのみ決定し、合格率、合格者数等によって変更されることはありません。合格点は、全建築委員会で共通です。
受験者の得点は、問題の統計的特徴(難易度、できる人とできない人との識別性の指標等)と受験者の能力レベルとの関係を判定する統計的モデル(アイテム・レスポンス理論)を使って採点されます。したがって、成績は、正解数ではなく、個々の問題のウエイトを考慮した得点となります。
試験問題は、各群とも同一の統計的基準に基づき、出題範囲、難易度をバランスよく組み合わせて構成されています。したがって、第1群で不合格と判定された人は、第2群から第4群へと問題を増やしたとしても、確立論的には合格はあり得ないとしています。ボーダーラインの人は、次の群へ進み、問題数を増やして合否を判定していきます。ボーダーラインの点数の幅は、第1群から第3群に進むにしたがって狭くなっていき、第4群ではその幅がなくなり合格、不合格のどちらかとなります。
(2)設計製図試験の採点
この試験を実用化するに当たっては、あらかじめ建築家委員会が客観的採点基準を開発し、コンピュータプログラムに導入しました。このプログラムの開発に当たっては、試験開発コンサルタントETS(教育試験サービス)に委託しております。1996年にフィールドテストを行い、コンピュータによる採点と従来の建築家による採点との評価の比較を行って、一部修正を加えています。
一つのビネット(小課題)には、説明の部分と製図の部分があります。説明の部分は、〈全体の説明〉〈設計条件〉〈コード〉〈ヒント〉の4つのメニューからなっています。15のビネットは、〈設計条件〉を少し変化させることにより、それぞれ24のバリエーションがあります。1998年には44バリエーションとなり、その後1年に12ずつ増やしていく予定とのことです。
ビネットによる試験では、例えば、部屋をデザインするとき、部屋の壁の線を1本1本描かせるのではなく、あらかじめ所定の部屋の形を用意しておき、それを受験者に配置させるようにします。採点は、その配置が〈設計条件〉に照らして、適当か否かを採点していきます。原則として、正解は一つではありません。また、受験者のコンピュータ操作の不慣れのためのミスか不適当な解答かを判断しなければなりません。採点は、全体論的方法で評価しますので、〈設計条件〉に照らしてテクニカルな部分が基準化された範囲内で正しければ、小さなミスは相殺されるようになっています。

コンピュータシステムの開発に参加したコンサルタントETS(プリンストン)
(3)試験結果の通知、再受験
試験結果については、試験センターから毎週、各州の建築家登録委員会に送られ、そこから受験者へ合否等が通知されます。不合格者には、成績が努力次第で改善されるものであるかどうかを示した診断情報も提供されます。
不合格になった科目については、6か月後以降でないと受験できません。不合格になった受験者には、再受験が可能になった時点で新しい受験許可証が送付されます。
6 おわりに
以上がアメリカで始まったコンピュータ化された建築家登録試験の概要です。翻って我が国の建築士試験のコンピュータ化を考えますと、コンピュータ化に向けた社会環境については、日本に比べてアメリカは、1.コンピュータの普及状況が相当進んでいること。2.試験センターの運営会社などが活動しており、コンピュータ化のインフラが整備されていること。3.試験理論やソフト開発などの専門コンサルタントのバックアップが得られること。などの違いがあります。
また、試験方式としては、例えば、1.出題した問題のうち一部は将来のためのデータ収集用で、採点対象外とすること。2.採点対象の問題は、全て既出の問題から出題せざるを得ないこと。3.設計製図の出題方式が小課題ごとに分けられており、一様の建物の全体設計とならないこと。等、我が国でそのまま採用することに疑問を持たざるを得ない部分もあります。
したがって、一朝一夕には我が国の現行の建築士試験をコンピュータ化することは難しいというのが率直な感想です。しかしながら、受験者の利便や建築実務におけるCAD利用の進展の状況から、いずれ我が国においても現行の紙と鉛筆の試験をコンピュータ化すべき時期が来るかもしれません。このため、当センターでは、今後とも試験のコンピュータ化に関する基礎的研究を続けて行くこととしています。