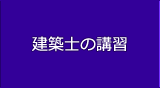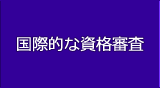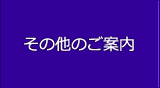国内外における試験のコンピュータ化の動き(1)
(財)建築技術教育普及センター建築技術者教育研究所
主任研究員 西原憲一
「QUA クウェイ」NO.22(2002年)より
1.はじめに
アメリカ合衆国のARE(建築家登録試験)は、1997年よりコンピュータ化されましたが、この実態についてはQUA CHANNELのNo.4で他の分野での動向等についてもNo.10で紹介しました。
その後、AREについては多肢選択式の出題形式が改正され、他の分野の試験でもTOEFLや情報処理技術者試験などにおいて、我が国に導入が実施・検討されるなどの動きが見られますのでこれらを2回に分けて紹介します。
2.アメリカの建築家登録試験
ア コンピュータ化試験の概要
建築家登録試験は、医師、教員などの資格試験を始めとする多くの試験と同様、コンピュータの画面上に問題が表示され、受験者はマウス等を使い直接解答する方式により実施しています。この方式では、試験は一斉に行うものではなく、試験会場の定員に合わせ受験者が希望する日に受験できます。出題される問題は、試験センターのサーバーに予めプール(収納)されている問題バンクから一定数選ばれ編集されますので、受験生により異なります。一方、それぞれの問題は他の受験生に何回も使用され、試験問題は非公開です(模擬問題は公表されています)。
イ 出題科目
多肢選択(四肢択一が基本)式の6科目と設計製図の3科目があり、これらの科目全てに合格しなくてはなりませんが、全ての科目を一斉に受験する必要はなく順次受験が可能です。ただし、不合格となった科目は6ヵ月を経過しないと再受験できません。科目の合格の有効期限は州等によって異なり、3年~10年など設定している州もありますが、4分の3以上の多くの州等では設定していません。
多肢選択式及び設計製図の試験科目の問題数と時間配分は表-1・2の通りです。
| 試験科目 | 問題数 | 試験時間 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 事前設計 | 125 | 3時間 | 3時間30分 |
| 一般構造 | 125 | 2時間30分 | 4時間 |
| 水平力 | 90 | 2時間30分 | 3時間 |
| 機械・電気システム | 125 | 2時間30分 | 3時間 |
| 材料・工法 | 125 | 2時間30分 | 3時間 |
| 工事書類・業務 | 125 | 3時間 | 3時間30分 |
- 各科目の出題数の中には、一部プレテスト用の問題が含まれている。これらの問題は、実際の試験の得点には影響を及ぼさないが、評価を行ったのち将来のテストに盛り込まれる可能性がある。
- 各試験において、試験時間の他に一般的指示説明、試験前に行われる学習プログラムによるチュートリアル(個別指導)、試験終了後の出口調査(アンケート)の時間が計30分ほど設定されている。
| 試験科目 | セクション | ビネット | 試験配分 (推奨時間) |
試験時間等 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敷地計画 | 第1セクション | 敷地デザイン | 1時間 | 2時間 | 5時間 |
| 敷地ゾーニング | 30分 | ||||
| 敷地パーキング | 30分 | ||||
| 休憩 | 15分 | ||||
| 第2セクション | 敷地分析 | 30分 | 1時間30分 | ||
| 敷地断面 | 30分 | ||||
| 敷地グレーディング | 30分 | ||||
| 建築計画 | 第1セクション | ブロックダイアグラム | 45分 | 1時間45分 | 7時間30分 |
| インテリアレイアウト | 1時間 | ||||
| 休憩 | 30分 | ||||
| 第2セクション | 基本計画 | 4時間 | 4時間 | ||
| 建築技術 | 第1セクション | 建物断面 | 1時間 | 1時間45分 | 7時間 |
| 構造レイアウト | 45分 | ||||
| 休憩 | 20分 | ||||
| 第2セクション | アクセス方法-傾斜路 | 45分 | 1時間45分 | ||
| 機械・電気設備計画 | 1時間 | ||||
| 休憩(任意) | 5分 | ||||
| 第3セクション | 階段設計 | 1時間 | 1時間45分 | ||
| 屋根伏図 | 45分 |
- 設計製図はCADを用いて行う。その採点はコンピュータによる自動採点で行われる。
- ビネットは小課題でこの集まりがセクションである。この2~3のセクションで1つの試験科目を構成している。
- ビネットごとに試験配分時間が想定されているが、実際の試験時間はセクションごとに設定されている。(同一セクション内では各ビネットにかける配分時間に制限はない)
- 試験時間や休憩の他に、各科目とも一般的指示説明、試験前に行われる学習プログラムによるチュートリアル(個別指導)、試験終了後の出口調査(アンケート)の時間が設定されている。
ウ 受験料と合格率
多肢選択式科目の受験料はそれぞれ92ドルであり、設計製図はそれぞれ143ドルです。また、過去3年間の各科目の合格率は61~90%(表-3)の範囲となっています(2000年10月に行った当センター職員によるNCARB担当者に対する聴き取り調査『以下「聴き取り調査」と略記』では各科目の合格率の目標は概ね8割前後と考えているとの回答)。
| 1998 | 1999 | 2000 | |
|---|---|---|---|
| 事前設計 | 63% | 69% | 73% |
| 一般構造 | 71% | 74% | 76% |
| 水平力 | 81% | 86% | 88% |
| 機械・電気システ | 80% | 85% | 77% |
| 材料・工法 | 88% | 89% | 90% |
| 工事書類・業務 | 82% | 84% | 85% |
| 敷地計画 | 71% | 72% | 72% |
| 建築計画 | 70% | 69% | 61% |
| 建築技術 | 72% | 75% | 78% |
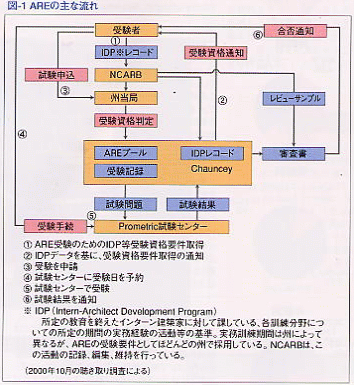
エ 試験実施機関
試験実施に関する主要な組織は、NCARB、Chauncey、Prometricの3つです。
NCARB(全米建築家登録委員会協議会)は、アメリカ各州等の法律によって設立された建築委員会をメンバーとする非営利法人でAREの実施・運営を取り仕切っており、各州それぞれの委員会はAREの結果等に基づき、所轄区域内での建築実務を行う免許の交付の決定についての最終的な権限を有しています。
Chauncey社は、TOEFLなど各種入学等試験を作成している教育テストサービス社(ETS:Educational Testing Service)の子会社であり、NCARBの試験開発及び業務のコンサルタントとしての役割を果たしています。さらにNCARBの委託を受け、受験資格情報の処理や受験許可証などの配布も行っています。
Prometric社は、入学等試験、免許・資格試験、ベンダー試験など様々なコンピュータベースの試験プログラムの実施に使用される試験センターの運営と維持管理を行っている会社で、その一つの試験としてAREを実施しています。
3機関と受験者の試験関係の主な流れは図-1の通りです。
オ 試験のコンピュータ化前後の動向
1997年のコンピュータ化開始時は多肢選択式科目ではCAT(注)方式を採用し、回答数や回答時間は出題者ごとに異なっていましたが、現在は回答数や回答時間を固定している方式に変更しました。変更した理由については聴き取り調査によると、プレテスト及びシステムの監督が非常に大変だったこと(特に、プレテストで正確な値を取るのが大変な上、経費がかかった)を挙げています。なお、設計製図については導入後に変更点はありません。
導入前の試験頻度は年1回(設計科目で年2回のものもあり)でしたが、導入後はテストセンターが空いていれば毎週月曜~金曜日のいつでも受験が可能となり、受験生の利便性は向上しました。一方、受験料は全科目合計485ドルでしたが、現在は981ドルとほぼ倍に値上げしました。
受験者数は、導入以前は年間概ね1万5千人(延べ受験者数は9万人弱)でしたが、導入後大幅に減少しその後は若干回復したものの約3分の1程度(2000年10月の聴き取り調査結果)です。
3.アメリカにおける試験のコンピュータ化
アメリカでは、主な大規模試験はコンピュータを用いた試験(CBT:Computer Based Testing)に移りつつあります(表-4)。
表-4 CBTを導入した大規模試験の例
- 各種入学等試験
SAT(公立大学入学試験)、GMAT(ビジネススクール入学試験)、GRE(大学院受験用試験)、TOEFL(外国人留学生英語能力試験)、 ASVAB(国防省式職業適性試験)など - 各種免許・資格試験
USMLE(医師免許試験)、NCLEX(看護士免許試験)、ARE(建築家登録試験)、PRAXIS(教育用専門試験)など - 各種ベンダー試験
Microsoft、Lotus、Oracle、Novellなど - 各種企業研修試験
これらの試験の出題形式の多くは、多肢選択形式又はその類似の形式ですが、中にはマルチメディア(音声・画像、写真、アニメ、ビデオ)なども利用し、支援ツールとして必要に応じて計算機、辞書、年表などをコンピュータ内に組み込むなど、従来の紙と鉛筆を用いた試験と比べ出題形式がバラエティーに富んでいます。さらに、構築式(エッセイ、シミュレーション・テスト、設計製図、数式展開、表計算など自ら解答を構築するタイプの問題形式)でもコンピュータ化されているものがあります。
多肢選択形式では、採点はコンピュータによる自動採点で行われますが、構築式のものは採点者が自ら採点するものもあり、この自動採点が大きな課題となっており、現在知識工学を応用した様々な研究が進められています(AREの製図試験はすでに自動採点を実施)。
参考文献
- ARE GUIDELINES(2001年) NCARB
- CBTにおける出題形式と採点法の展望(e-Learning Forum Winter Handout Book(2001年))池田央
注)CAT(Computerized Adaptive Testing)
コンピュータが受験者の解答結果をもとに、能力レベルを逐次推測しながら、そのレベルに合わせた問題を集中的に出題する方式のテスト