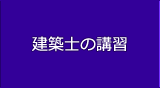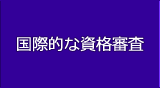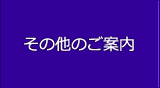令和7年度 建築技術の調査研究又は普及活動を応援する助成の決定について
4月から5月にかけて公募した標記の助成について、数多くの申請をお寄せいただきありがとうございました。このたび、下記の通り助成対象を決定いたしましたのでお知らせいたします。
審査経過
助成対象の選考に当たっては、審査委員会を設けて慎重に審査を行い、その審査結果を踏まえて助成対象を決定いたしました。
建築技術の調査研究又は普及活動を応援する助成審査委員会(敬称略 五十音順)
委員長 澤地 孝男 (国立研究開発法人建築研究所)
委 員 五十子 幸樹 (東北大学)
委 員 蟹澤 宏剛 (芝浦工業大学)
委 員 中埜 良昭 (東京大学)
委 員 西川 豊宏 (工学院大学)
委 員 西野 辰哉 (金沢大学)
委 員 林田 康孝 (建築技術教育普及センター)
委 員 松田 雄二 (東京大学大学院)
講評
建築技術の調査研究又は普及活動を応援する助成審査委員会
(公財)建築技術教育普及センター
本助成制度は、建築技術の教育普及が一層促進されることを目的として、平成22年度に実質的に開始されたもので、今年度で16年目を迎えます。今年度も、幅広い活動内容に関して多くの意欲的な応募をいただきました。本制度の活用により、建築技術の教育普及が一層促進されることが期待されます。
審査に当たっては、以下に記載する観点から各審査委員間で議論を進め、評価を実施しました。
評価基準
調査・研究、普及活動を区別せず募集を行い、以下の評価基準の観点等を中心に審議し、審査を行いました。
- 調査・研究が目指そうとしている成果により、建築技術者の啓発や資質の向上が図られること、国民の建築技術者への理解や信頼を深めることが期待できること、または、建築実務、教育制度のあり方等を提案しようとするものであること。
- 調査・研究の実施方法や体制・行程が明確で実行可能なものであり、掲げた調査・研究の目標を達成しうると判断できること。
- 調査・研究の目的や内容に新規性、独自性が高く、今後の展開の可能性があると判断できること。
- 普及活動を通じて広めようとする内容が、建築技術者が体得すべき建築実務面で有用な知見である、若しくは、国民の建築技術者への理解や信頼を深めるものであると判断できること。
- 講演会などを企画・実施する方法や体制・工程が明確で、実行可能なものであり、期待する効果が発揮できると判断できること。
- これまで毎年問題なく実施している等、申請者の本来の活動として行うべきと考えられるものではないこと。
審査委員会による審査を踏まえて、8件を助成の対象として決定しました。
なお、継続的な応募案件については、これまでの成果や採択継続の必要性について議論を行ったうえで、評価基準(募集案内に掲載)に照らして、選考・決定しました。
助成対象として決定された案件及び案件ごとの選評は、下記の一覧表に掲載しているとおりです。
助成対象案件
助成対象案件(令和7年度分)8件 〔順不同〕
| 名 称 | 実施者 | 選 評 |
|---|---|---|
| 土木工学科を母体とする地方大学・高専における構造・設備分野等の建築・土木融合授業の開発と高校生らの意識 | 多田 豊 (愛媛大学大学院理工学研究科環境建設工学講座・准教授) |
細分化された技術分野では解決しにくい社会課題が増えてきている現在において、建築と土木の融合カリキュラムについて検討することは評価できる。本成果を積極的に発信することにより教育機関における建築教育の発展に繋がることを期待したい。 |
| 国際通用性あるオフショア型建築教育活動に関する調査研究 | 田中友章 (明治大学理工学部建築学科・専任教授) |
資格の国際通用性の確保が求められる世界潮流のなかで、日本に必要とされる資格制度・教育システムに関する知見を得ようとするもので、国際的な連携体制の下でこれを実現しようとすることは評価できる。今後の教育体制に必要な知見をわかりやすい形でとりまとめ発信することで、これに基づく国際通用性あるオフショア型建築教育活動が展開されることを期待したい。 |
| 地震で被災した伝統的建造物群保存地区における建築構造学的復旧支援システムの構築 | 西川 英佑 (関西大学・助教) |
能登半島地震からの復興において、輪島地域固有の風景を作っている被災古民家を残して活用することを目指し「構造的な補強修理に関する有用な知見」を蓄積する重要な研究と評価できる。本活動により作成される伝統木造建築の応急補強の設計施工マニュアルや、被災建物の修理補強におけるチェックシートが将来の被災古民家の復興にも役立つものとなることを期待したい。 |
| 建築模型の揺れを簡単に計測できる加速度センサによる建物構造振動教育ツール | 池田雄一 (高知工業高等専門学校 准教授) |
地震災害の多い我が国において、建築構造の実践的な教材(建物構造振動教育ツール)を作成し、建築教育に活用することは評価できる。本教材が多くの教育機関で活用され、建築構造技術者教育の発展に繋がることを期待したい。 |
| いつでも、だれでも、だれとでも-分譲マンションの維持管理と防災設備を学ぶオリジナル教材のWeb配信 | 辻井左恵 (特定非営利活動法人集合住宅維持管理機構・事務局長) |
近年問題が先鋭化しつつあるマンション管理と防災というテーマを扱い、また教材のオンライン化も意図する事業である。オンライン化するだけにとどまらず、その周知の方法を工夫することにより、だれでも、学校教育でも使えるようにすることで、成果が広く還元されることを期待したい。 |
| 建築倫理教材「先達に聞く」 | 小野田泰明 (一般社団法人日本建築学会 会長) |
日本の高度成長期に第一人者として技術者を育てた先達の功績は大きく、建築倫理に関するその考え等をアーカイブ化することは評価できる。建築技術者の倫理的判断や行動規範に資する教材として安定的かつ持続的な活用がされることを期待したい。 |
| 建築士の日事業(連合会記念講演) | 古谷 誠章 (公益社団法人日本建築士会連合会 会長) |
住宅のヒートショック、熱中症予防と住宅の断熱改修という国民の命に関わる重要なトピックに関する講演会(動画配信)であり、地域の人々に住宅の断熱改修等のアドバイスができる建築技術者への信頼を深め活躍の場を広げる取組の一環と評価できる。その成果が建築技術者に限らず国民に還元されることを期待したい。 |
| 既存住宅活用ガイド(仮称)の制作および普及事業 | 青木 千枝子 (一般財団法人住まいづくりナビセンター) |
住宅の性能更新などのための既存住宅活用ガイドを製作し、住み慣れた我が家の性能を高め快適に住み続けられるよう一般のユーザーでも理解できるWEBツール化することは評価される。その成果が広く国民の住まい環境の向上に対して還元されることを期待したい。 |