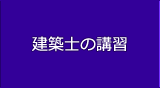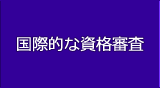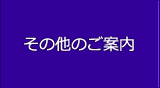知的財産権と建築
(財)建築技術教育普及センター建築技術者教育研究所長
小泉重信
「QUA クウェイ」NO.17(2000年)より
情報技術(IT)革命によるコミュニケーションの技術が進展すれば、また別の問題が発生します。その一つに知的財産権の問題が挙げられます。建築は、特定の土地に特定の条件で建てられるもので、全くの同一性はないはずですが、工業化の進展による大量生産や、情報メディアの発達により、知的財産権に関する問題も多くなっています。
知的な創作活動は人間性を表わした最も高度なものです。その成果を多くの人が享受したいという欲望があります。創作活動の活発化のため創作者成果に対する評価と、その成果利用のための普及策とが求められますが、この両者の要求には相矛盾した所があり、コストを負担して両者の要求を満足させる制度として著作権や特許権の制度があります。
1 知的財産権の歴史
知的財産権の歴史は古く、特許権は13世紀のイギリスの織物技術特許に、著作権は15世紀のドイツの印刷技術の発達に伴う海賊版防止のための複製権として始まっています。 更に国際条約としては、1883年のパリ条約、および、1886年のベルヌ条約がその始まりです。
1967年のWIPO(World Intellectual Property Organization)(注)という世界機関の設立をきっかけに、諸権利が、知的財産権として総合化されました。WIPOのわが国での正式名は「世界知的所有権機関」ですが、IPは原義的には知的財産権です。工業所有権という語があるので、その延長でIPも知的所有権になったかと思われます。人により使い方がまちまちですが、内容は全く同一です。
WIPOは世界的に知的財産権の保護を促進、改善することを目的に設立され、条約の締結、改正、各国法律の調整を実施してきました。最近では、世界共通特許(World Patent Network)を目指していますが、知的財産権については、いわゆる南北問題があり、利害が一致しないこともあって、主要舞台はWTOに移行しつつあるようです。
2 知的財産権(知的所有権)の構成と建築
WIPOの定義による知的財産権は、大別して二つの範疇、七つの項目に分けられます。
(A) 著作権――――(1)文芸、美術、学術の著作物、 (2)演奏、レコード、放送
(B) 工業所有権――(3)発明、(4)科学的発見、(5)意匠、(6)商標、商号、(7)不正競争保護
わが国の著作権法により保護される著作物の具体例の一つに「建築の創作物」があり、学術的、美術的な創作表現と認められたものに限定して、対象とされます。
著作権侵害等についての判断基準として、同一性の基準がありますが、建築物は厳格な意味での同一性を評価することは非常に困難です。しかし、判例では、基本的な構造や全体的な類似性のほか、設計上の自由度の大きさ等を斟酌して判断されているようです。
3 UIAにおける建築分野の知的財産権に関する指針案
UIA(世界建築家連合:Union Internationale des Architectes)は、1999年6月の北京大会において、「建築業務における専門職能性の国際推奨基準に関するUIA協定」を原則承認しました。現在は、専門委員会であるPPC(専門職能プログラム)で、業務の形態、団体の役割、知的財産権等の事項に関する指針について、検討が進められています。ここでは、知的財産権に関する推奨指針案について示します。
「UIAの知的財産権と著作権に関する推奨指針案」の概要
(1)著作者
著作者は、著作物の創作者である自然人に限られ、法人や企業は著作者にはなれない。
(2)保護される著作物
(2)-1 建築の著作物
保護される著作物とは、建築の平均的デザインレベルを上回る個人的創作をいい、純粋に技術的な計算に基づく著作物や偶然の一致による創作は保護されない。保護は有形の著作物のみに適用され、単なるアイデア等には適用されない。
(2)-2 特殊な建築著作物の保護
(2)-2-1 専門家の意見書、仕様書、その他の資料
専門家の意見書、仕様書、その他の資料は、これらが平均水準を超えるデザインの個人的創作であれば保護される。著作権を工業所有権と区別するため、保護は資料の内容には及ばず、あくまで表現の形態のみに適用される。
(2)-2-2 スケッチ、青写真および平面図
建築物のスケッチ、青写真および平面図は、そのデザインのみならず、計画の内容についても3次元で表わされるものは保護される。
(2)-2-3 建築物
著しくデザインの独創性が高く個人的創作の要件を満たす場合は、建築物の部分でも、また結合体でも保護される。要素部分は既知でも全体として新規の創作的結合体ならば保護される。創作的要素の判断には形態、様式、美的価値、流行の別は問わない。
著作権保護の著作物として建築物用途の別も問わない。
(3)著作者利益の保護
(3)-1 公表権
著作者は、著作物を公に情報伝達することの可否決定の権利を専有する建築設計競技で作成されたスケッチについては、建築家の同意を得た場合のみ公表できる。
(3)-2 氏名表示権
著作者は著作物に氏名を表示する権利を有する。スケッチ、平面図、施設についても同様。著作権表示は保護の条件ではないが、透明性のために表示されるべきである。著作権表示の例としては、"Copyright (c) Associated Architects、Inc.2000”が考えられる。
(3)-3 権利侵害
経済的権利の譲渡後であっても、原著者としての権利を主張できる。当該著作物の盗作、歪曲、切除、その他の改変により著作者に名誉毀損のおそれがある行為に対し侵害の停止を請求する権利を有する。経済的権利は、著作者の死後、有効期間まで保持される。
(3)-4 解体除却
著作物改変拒否権には、除却解体拒否権も含まれる。除却解体の場合には、その建築家が改変著作物の著作者として誤認されることはないが、著作者の同一性保持権が侵害される。
(4)客側の改変の利益と著作者側の同一性保持の利益との衝突
著作者は、著作物の改変を禁止する権利、原型で再建築するよう要求する権利を有する。改変は、建築物の同一性保持に関する著作者個人の利益が安全に守られ、著作者の建築的能力の評価が公然と落ちることがないよう確実にしなければならない。他方、建築物の所有者または利用者は、変化するニーズや目的に対し、建築物を適応させる権利を持つが、建築的コンセプトを変えてしまうことがある。
従って、二つの対立する利害のバランスを見つけることが必要になる。即ち、顧客の改変の利害と著作者の同一性保持権の利害との対立である。このバランスを見つけるにあたり、原建築家のみが、建築物の設計とその美観性に関し、必要な解決策を探せる最良の立場におり、他の誰よりも需要の変化に対する建築物開発の可能性について、最も洞察していた事実を考慮するべきである。建築物は、長期の間には、模様替え、増築、その他の変更が必要になる可能性があり、建築物の存続中、別の特別な建築家の手を借りる必要性が出ることもある。
建築物の著作者は、顧客の改変希望に応えて建築的解決策を提案する契約上の権利を有しなければならない。この契約条項によって、建築物は、最高の質を維持しつつ要求に応え、原型の建築表現の保護にも適応するものとなろう。当該建築家が業務を遂行できないとか、する意思がない、また、他の事情で施主が原建築家を雇うことができない場合にのみ、他の建築家を改変計画に雇うことができるものとする。
(5)保護の期間
保護期間は著作者の存命中および死後50年とする。UIA会員地域はこれを超える保護期間を認めることができる。
(6)知的財産権の執行
UIA会員地域は、知的財産権の侵害行為に対し、法律による権利侵害防止策の確実な執行に努めなければならない。これにより公正取引上の障害の発生および乱用を回避することができる。知的財産権の執行手続きは公明、公正でなければならない。不必要に複雑、高費用、不合理な時間制限、保証のない遅延があったりしてはならない。
賠償額の決定は、書面により判定され、当事者に遅滞なくなされなければならない。この場合、当事者に聴聞の機会が与えられるので明白な根拠に基づかなければならない。
(7)UIA会員地域間の協力
各UIA会員地域は、本指針の主要事項を侵害して業務していることを信ずる十分な理由がある場合、要求により、他のUIA会員地域と協議に入らなければならない。
(8)損害
UIA会員地域は、司法制度により当局に対し、権利違反者が権利保有者の蒙った損害に対し十分な賠償を支払うよう命じなければならない。
(9)団体の整備:最終条項
UIAは、本指針の運用、義務に関するUIA会員の不平について監視し、知的財産権に関する相談の機会を提供しなければならない。各UIA会員地域は責任を果たし、紛争処理手続き上必要な支援を提供し、知的財産権を侵害する国際商品取引を排除するため相互に協力することに同意する。
以上が指針案の内容です。この指針案でいう「知的財産権」はわが国の「著作(財産)権」に、また、「著作権」は「著作者人格権」に相当しているようです。著作者については自然人の原著作者に限定していますが、わが国の著作権法では、雇用者が職務上作成する著作物について法人や使用者が著作者となることを認めています。また、(4)の建築物所有者の改変要求利害と建築家の同一性保持権利害との対立に関しては、バランスが重要と言いつつも、改変に対する原建築家の権利が強く、再契約の既得権性を含め、いささか建築家至上主義に走り、顧客満足度に対する配慮が乏しいように見えないでしょうか。
参考資料『知的財産権と消費者』東京都消費生活総合センター、2000年3月
『時の動き』総理府2000年9月
注:WIPO(世界知的所有権機関、World Intellectual Property Organization)
1967年、知的財産権を全世界にわたり尊重、保護するために設立された国連の専門機関の一つ。本部はジュネーブにあり、その目的とするところは、(1)加盟国間の協力及び他の国際機関との協調による知的財産権(著作権・工業所有権)の世界的保護の促進、(2)知的財産権に関する諸同盟の間での行政的協力の確保にある。2000年7月現在、175ヵ国が加盟。わが国は1975年に加盟。
| 対象 | 根拠法 | 保護期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 知的財産権 (知的所有権) (無体財産権) |
工業所有権 (広義) |
工業所有権 (狭義) |
特許権 | 発明 | 特許法 | 20年 |
| 実用新案権 | 考案 | 実用新案法 | 6年 | |||
| 意匠権 | 工業デザイン | 意匠法 | 15年 | |||
| 商標権 | 商品・役務商標 | 商標法 | 10年 | |||
| 不正競争防止法 | 営業表示・秘密 | 不正競争防止法 | ||||
| 半導体集積回路配置法 | 半導体集積回路図 | 半導体集積回路配置法 | 10年 | |||
| 種苗法 | 種苗品種 | 種苗法 | 20,25年 | |||
| 商法(商号) | 商号 | 商法 | ||||
| 工業所有権 (広義) |
工業所有権 (狭義) |
著作権 (狭義) |
著作物 | 著作権法 | 死後50年 | |
| 著作者人格権 | 著作者 | |||||
| 著作隣接権 | ||||||