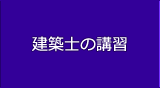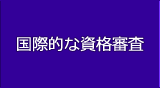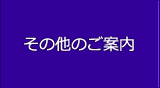Q&A
(APECエンジニアについて)
Q1.
APECエンジニアとは何ですか?
A.
実務経験などについて一定レベル以上にあると認められる技術者に対する、APEC域内の共通の称号です。
今後、関係する二国間または多国間の政府間での協議が整えば、相互承認の段階に移行することになります。(この場合、協議の内容如何によっては、相互承認のための補足審査や追加的条件等が課せられる場合があります。)
Q2.
APECエンジニアは、国家資格ですか?
A.
APEC参加国間で一定レベル以上の技術者に対し、APEC域内の共通の称号を与えられるもので、国の法律に基づく資格等の登録ではありません。
日本では、12省庁(1999年11月当時。現在は、関係9省)の申し合わせに基づき設置されたAPECエンジニア・モニタリング委員会で審査登録等が行なわれているものです。(建築構造分野については、モニタリング委員会の委託を受け、建築エンジニア資格委員会(事務局:センター)が審査登録等を行います。)
Q3.
APECエンジニアになるとどんな仕事ができるのですか?
A.
APECエンジニアとは「称号」ですので、直接仕事に結びつくことはありません。APECエンジニアとしての登録は、技術者としての能力がAPEC域内で同等であるとみなされることです。資格の受入れについては今後、関係する二国間または多国間の政府間での協議が整えば、相互承認の段階に移行することになります。
Q4.
APECエンジニアになるにはどのようにしたらよいですか?
A.
必要書類を揃え、APECエンジニア事務局へ提出してください。提出後、APECエンジニアの7要件についての審査(書類審査と必要に応じて面接審査)で要件を満たしていると認められた後、登録を受ける必要があります。
Q5.
APECエンジニア7要件とは何ですか?
A.
(1)登録、免許の要件としての総合的学力レベルを有していること。
(2)International Engineering Alliance(IEA)が標準として示すエンジニアとしての知識・能力に照らし、自己の判断で業務を遂行する能力があると認められること。
(3)エンジニアリング課程修了後、7年間以上の実務経験を有していること。
(4)(上記の7年間のうち)少なくとも2年間は重要なエンジニアリング業務の責任ある立場での経験を有していること。
(5)継続的な専門能力開発を満足すべきレベルで実施していること。
(6)業務の履行に当たり倫理的に行動すること。
(7)プロフェッショナル・エンジニアとして行った活動及び決定に対して責任を持つこと。
Q6.
日本が登録しているAPECエンジニアの専門分野は何ですか?
A.
日本が登録を開始している専門分野は、「Civil」「Structural」「Geotechnical」「Environmental」「Mechanical」「Electrical」「Industrial」「Mining」「Chemical」「Information」「Bio」の11分野です。
専門分野の定義は各エコノミーによって相違があります。
Q7.
どのような人が審査の申請をできるのですか?
A.
日本では、Structural分野のうち建築構造分野は、一級建築士資格取得者の内、建築構造に携わる方が審査対象者となります。
上記以外のStructural分野とその他の分野は、技術士資格取得者が審査対象者となります。
Q8.
APECエンジニア事務局はどこですか?
A.
- Structural分野のうち建築構造分野:公益財団法人 建築技術教育普及センター(当センター)
- 上記以外のStructural分野とその他の分野:公益社団法人 日本技術士会
(上記、2つの分野で、審査・登録等の方法が違います。)
Q9.
APECエンジニアの称号には有効期限があるのですか?
A.
登録証交付日より5年間です。その後もAPECエンジニアであり続けるためには、登録の更新を行う必要があります。具体的には、登録の更新のための審査において要件を満たしていると認められなければなりません。
(新規申請書類について)
Q1.
申請書類はどこで入手できますか?
A.
センターのホームページよりダウンロードできます。
Q2.
審査申請書の提出はどのようにするのですか?
A.
申請に必要な書類をセンターまで簡易書留により郵送で申請して下さい。(普通郵便で紛失等の場合の責任は、負いかねますのでご了承下さい。)
Q3.
審査手数料、登録手数料はいくらですか?
A.
審査手数料は13,200円(うち、消費税額1,200円)、登録手数料は8,800円(うち、消費税額800円)です。
Q4.
申請回数に限度はありますか?
A.
ありません。
Q5.
申請書は日本語と英文のどちらを提出するのですか?
A.
申請書は日本語、英語の両方を提出して下さい(様式4 CPD実施記録簿は日本語のみ)。提出されない場合は、書類不備で審査対象になりません。ただし、審査は、日本語で行います。
また、申請書の記載内容は、日本語と英語で相違のないよう記入して下さい。相違が見受けられた場合、審査できない場合や要件を満たすと認められない場合があります。
Q6.
英語の申請書はなぜ必要なのですか?
A.
APECエンジニア参加国で構成されるAPECエンジニア協定総会による監査や各国からの問い合わせ等に対応していく必要があります。
Q7.
英語能力の審査があるのですか?
A.
英語能力の審査はありません。
Q8.
なぜ、申請書類に一級建築士の免許証若しくは免許証明書の写し又は建築士登録証明書が必要なのですか?
A.
APECエンジニアの要件を満たすためには、一級建築士として有効に登録されていることが必要であることから、その確認が必要です。なお、一級建築士の免許証または免許証明書の写しを提出してください。また、一級建築士登録証明書を提出する場合には、各県の建築士会で発行を受けて下さい。(有料となっております。)
Q9.
一級建築士免許証または免許証明書の原本照合は、登録した都道府県で行わなければならないのですか?
A.
一級建築士の免許証または免許証明書の写しを提出してください。また、一級建築士登録証明書を提出する場合には、各県の建築士会で発行を受けて下さい。この手続き(有料)等については、全国の建築士会に問合せ下さい。
Q10.
一級建築士免許証または免許証明書の再交付手続き中の場合はどのようにしたら良いですか?
A.
建築士登録証明書を提出して下さい。
Q11.
大学のエンジニアリング課程とは何ですか?
A.
大学での基礎工学分野(数学、物理等を含む)や建築等の専門に関する課程のことですが、Structural分野に申請する建築構造技術者の場合は、一級建築士の受験資格において、必要な実務経験が2年である課程が「大学のエンジニアリング課程」と判断されます。なお、「大学のエンジニアリング課程」を修了していない場合については、学歴、二級建築士の有無及び実務経験年数等を考慮し、モニタリング委員会が「大学のエンジニアリング課程」修了と同等かどうか判断します。
Q12.
エンジニアリング業務に大学院での研究は含みますか?
A.
大学院での研究はエンジニアリング業務になり得ません。建築構造に関する実務とは、構造設計、構造計算、建築士法第2条第8項の工事監理等をいいます。
Q13.
(様式1)「学歴」欄は、どの学歴から記入すれば良いですか?
A.
高校等の普通科での修了部分を除き、工学教育を受けたものについて記入して下さい。ただし、工学教育を受けていない方は、最終学歴を記入して下さい。
Q14.
学歴が5つ以上の場合はどのように記入するのですか?
A.
工学教育の学歴だけで5つ以上の場合は、最終学歴から記入するようにして下さい。
Q15.
(様式2、3)「申請者の果たした役割」、(様式3)「プロジェクトの特徴」欄に書ききれない場合はどのようにしますか?
A.
文字制限を守り、欄内に収まるように記入して下さい。ただし、Form3(様式3の英文様式)については、”Roles performed while you were in “responsible charge” of significant engineering work” の記入が所定の欄に収まらない場合、収まらない分を記入した別紙(A4サイズ。様式任意。)を次のページに添付して下さい。
Q16.
(様式2、3)「構造エンジニアとしての担当期間」とは何ですか?
A.
プロジェクトの期間ではなく、そのプロジェクトの中で構造エンジニアとして携わった期間を記入して下さい。
Q17.
(様式2、3)「構造エンジニアとしての担当期間」に記入した期間が複数のプロジェクトで重複しても良いのですか?
A.
同一時期に複数のプロジェクトに従事し、期間が重複する場合は、実務経験の期間として重ねてカウントすることはできません。
Q18.
APECエンジニア要件の「エンジニアリング課程修了後、7年間以上の実務経験」とは、一級建築士取得後の実務経験を意味するのですか?
A.
一級建築士受験資格に基づく大学課程を修了した方については、大学のエンジニアリング課程修了後の実務経験を意味します。
大学課程を修了していない方については、一級建築士試験登録後の実務経験を意味します。
Q19.
APECエンジニア要件の「エンジニアリング課程修了後、7年間の実務経験」とは、どのような実務を申請すれば良いのですか?
A.
建築構造及びそれに明確に関連性を有する実務のみを最近のものから新しい順序で、期間を重複せずに7年間以上について記入して下さい。
上記の実務以外のものは認められませんので、疑わしいものについては、詳しく記入して下さい。審査において総期間数が7年間(84ヶ月)を下回る可能性がありますので余裕をもって申請して下さい。
Q20.
APECエンジニア要件の「2年間以上の重要なエンジニアリング業務の責任ある立場」とはどのような立場ですか?
A.
一級建築士資格取得(登録)後の責任ある立場として担当した業務について記入して下さい。取得前(登録前)の業務はカウントされません。
(二級建築士資格取得(登録)のみの立場で担当した業務についてカウントはできません。)
Q21.
様式3の図面等は、どのような書類を提出すれば良いのですか?
A.
構造上の特徴を示す設計図等に限ります。(写真やパースのみでは、図面等の書類として認められません。)縮尺は自由です。 なお、A4サイズ、複数枚以内に収めるようお願いします。
Q22.
(様式3)「第三者証明」欄は、いくつかのプロジェクトが同じ上司の氏名になっても全ての様式に自署してもらうのですか?
A.
1プロジェクトごとに第三者証明が必要になります。第三者証明のないプロジェクトは、実務経験として認められません。また、自署のコピーは不可です。
Q23.
(様式3)「第三者証明」欄は、申請者自身が部長等であった場合どのような方に自署してもらえばよいですか?
A.
上司には役員を含めて結構です(その場合、所属部署の記載は不要です)。なお、構造設計部長等の場合、他の部門の長や共同事業担当者等、申請書の業務の実施を証明できる方に限ります。(申請者の友人又は部下の方は除きます。)
Q24.
(別紙)推薦書の「推薦者氏名」欄はどのような方に自署してもらえば良いですか?
A.
推薦する時点において一級建築士として登録されている方で、2名分必要です。年齢、一級建築士登録後の年数、居住地域、申請者との面識年数、APECエンジニア資格の有無は問いません。ただし、推薦時点において、申請者及び申請内容をよく理解している方に限ります。
(登録の更新審査申請書について)
Q1.
更新のための審査とはどのような審査ですか?
A.
APECエンジニアの7要件のうち、「継続的な専門能力開発(CPD)を満足すべきレベルで実施していること 」について審査を行います。また、一級建築士として有効に登録されていることを合わせて確認します。
Q2.
申請書類はどのようにして入手できますか?
A.
更新対象者には、センターから直接本人あてに原則、登録の有効期限の半年前までに更新審査申請の書類を送付します。
Q3.
審査申請書の提出はどのようにするのですか?
A.
申請に必要な書類をセンターまで簡易書留(又はレターパック)により郵送で申請して下さい。(普通郵便で紛失等の場合の責任は負いかねます。)
Q4.
更新審査・登録手数料はいくらですか?
A.
11,000円(うち、消費税額 1,000円)です。
Q5.
なぜ申請書類に一級建築士の免許証若しくは免許証明書の写し又は建築士登録証明書が必要なのですか?
A.
APECエンジニアであり続けるためには、一級建築士として有効に登録されており、かつ一定期間毎に要件(5)「継続的な専門能力開発(CPD)を満足すべきレベルで実施していること 」を満たす必要があることから、その確認が必要です。なお、一級建築士の免許証または免許証明書の写しを提出してください。また、一級建築士登録証明書を提出する場合には、各県の建築士会で発行を受けて下さい。(有料となっております。)
Q6.
一級建築士免許証または免許証明書の原本照合は、登録した都道府県で行わなければならないのですか?
A.
一級建築士の免許証または免許証明書の写しを提出してください。また、一級建築士登録証明書を提出する場合には、各県の建築士会で発行を受けて下さい。この手続き(有料)等については、全国の建築士会に問合せ下さい。
Q7.
一級建築士免許証または免許証明書の再交付手続き中の場合はどのようにしたらよいですか?
A.
建築士登録証明書を提出して下さい。
(CPDについて)
Q1.
CPDとは、何ですか?
A.
Continuing Professional Developmentといい、継続的な専門能力開発のことです。具体的には、専門家として必要な知識及び技能の維持向上に努めることを言います。
Q2.
APECエンジニアに何故CPDが必要なのですか?
A.
APECエンジニアになるための7要件の1つに「継続的な専門能力開発を満足すべきレベルで実施していること」とされているためです。
Q3.
APECエンジニアのCPDは、何時間必要とされているのですか?
A.
新規申請の場合には、審査申請書受付開始前の2年間に100時間が必要です。
登録の更新の場合には、審査申請書受付開始前の5年間に250時間が必要です。
Q4.
登録の更新に必要なCPD時間数が要件の250時間に満たない場合は、どうなりますか?
A.
登録の更新の要件を満たすことが認められないため、登録が失効します。
ただし、「遡及登録更新」、または「再登録」が可能です。詳しくは、登録の更新審査申請案内「5.遡及更新登録」「6.再登録」をご覧下さい。
Q5.
どのようなCPDが認められるのですか?
A.
建築CPD情報提供制度認定プログラムへの出席記録(受付時に名簿へ記載したもの)は、APECエンジニアのCPDとして認められます。(更新の場合に限る。)その他のプログラムについては、申請内容を審査します。内容が不明確等の場合、別途書類の請求又は問合せをする場合があります。
Q6.
海外で受講した講習会などはCPDとして認められますか?
A.
国内、海外問わず申請していただいて結構です。ただし、内容については審査を行います。そのため、申請者に問合せ又はそれについての追加書類を請求する場合があります。
Q7.
参加学習型及び情報提供型には上限がありませんが、これらの形態で要件の時間数を満たしてもよいですか?
A.
かまいません。ただし、1つのプログラムが長時間又は分野が偏っている場合には、審査の過程で問い合わせ又は資料の請求等をいたしますので、CPDに関する資料は保管しておくようにして下さい。
Q8.
新規の申請において、実務学習型は様式3で記入した業務でもよいですか?
A.
かまいません。ただし、CPDとして認められる期間は申請時より直近2年間分となっていますので、2年を超える以前の業務は認められません。