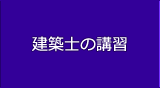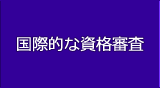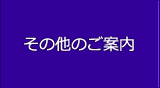構造/設備設計一級建築士講習の受講資格等のよくある質問
2023年5月15日
目次
1.講習全般に関する質問
Q1.
平成18年12月改正建築士法はいつ施行されましたか。
A1.
平成20年11月28日に施行されました。
Q2.
この講習と、平成18年12月改正建築士法の施行前に実施されたみなし講習の内容は同じですか。
A2.
ほぼ同じ内容となっています。
Q3.
今回の講習以降の予定は。
A3.
令和6年度以降も年に一度講習を実施する予定ですが、詳細が決まり次第発表します。
2.受講手数料に関する質問
Q1.
受講手数料は。
A1.
(1)構造設計一級建築士講習
申込区分I(全科目受講) :55,000円(消費税込み)(令和3年度又は令和4年度受講者については49,500円(消費税込み))
申込区分II(法適合確認のみ受講) :44,000円(消費税込み)(令和3年度又は令和4年度受講者については38,500円(消費税込み))
※令和3年度又は令和4年度講習で構造設計の修了者
申込区分III(構造設計のみ受講) :49,500円(消費税込み)(令和3年度又は令和4年度受講者については44,000円(消費税込み))
※令和3年度又は令和4年度講習で法適合確認の修了者
(2)設備設計一級建築士講習
申込区分I(全科目受講) :66,000円(消費税込み)(令和4年度受講者については60,500円(消費税込み))
申込区分II(法適合確認のみ受講) :44,000円(消費税込み)(令和4年度受講者については38,500円(消費税込み))
※令和3年度又は令和4年度講習で設計製図の修了者
申込区分III(設計製図のみ受講) :55,000円(消費税込み)(令和4年度受講者については49,500円(消費税込み))
※令和3年度又は令和4年度講習で法適合確認の修了者
申込区分IV(建築設備士) :44,000円(消費税込み)(令和4年度受講者については38,500円(消費税込み))
Q2.
仕事の都合等でどうしても受講できない場合は、受講手数料を返してもらえますか。
A2.
講習に欠席した場合は、受講手数料の返還はしません。
ただし、事前に連絡があれば、空き状況によっては他の講習地の案内を行います。
Q3.
講義は出席したが、修了考査に出席できない場合は受講手数料を返してもらえますか。
A3.
当センターの責による事由でない限り、講習の欠席での受講手数料の返還はしません。
3.受講申込の配布に関する質問
Q1.
受講申込書の配布はいつからですか。
A1.
受講申込は、原則として、インターネットによる受付のみとなりますので、受講申込書の配布は行いません。
ただし、インターネットによる受講申込が行えない正当な理由がある場合(身体に障がいがありインターネットの利用が困難である等)には、別途受付方法をご案内いたしますので、受付期間に間に合うよう、お手数ですが6月23日(金曜)までに、構造設計一級建築士講習問合せダイヤル(電話050-3033-3826)又は設備設計一級建築士講習問合せダイヤル(電話050-3033-3827)までお問合せ下さい。
4.受講申込の受付に関する質問
Q1.
受講申込の受付期間はいつですか。
A1.
令和5年6月12日(月曜)午前10時から6月30日(金曜)午後4時まで受付けます。
Q2.
申込方法を教えてください。
A2.
受付期間に構造(又は設備)設計一級建築士講習の申込サイトで必要な情報(業務経歴書・業務経歴証明書を含む。)を入力し、顔写真及び受講申込に必要な書類の電子ファイルを取り込んで受付システムの所定の場所に添付し、センターの指定するクレジットカード、コンビニエンスストア又はペイジーのうちいずれかの決済方法により受講手数料を納付して下さい。詳細はセンターホームページに掲載の構造(設備)設計一級建築士講習受講要領でご確認下さい。
Q3.
受講会場の希望は、先着順ですか。
A3.
申込順となります。
Q4.
受講を申込し込んだが、どの講習会場も空きがない場合はどうなるか。
A4.
講習会場については収容人数に余裕をもって確保しております。万が一申込者数が会場収容人数を超えた場合には、会場の変更又規模拡大をすることで、ご希望どおりの会場で受講できるよう対応いたします。また、講義については、会場での受講方式に代えて、配信動画の視聴による受講方式を選択することができますので、よろしければご検討下さい。
5.受講資格に関する質問
Q1.
受講申込に必要な書類は。
A1.
一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書の電子ファイルと、構造設計又は設備設計の業務経歴書・業務経歴証明書(受付システムに入力フォームがあります。)が必要です。
また、講習の免除措置を希望する場合は、免除措置に必要な書類の提出が必要です。詳細はセンターホームページに掲載の構造(設備)設計一級建築士講習受講要領でご確認下さい。
Q2.
建築設備士の資格を取得して5年以上の建築設備設計に関する業務従事しています。令和4年の一級建築士試験を受験して合格しましたが、受講申込の受付期間までに一級建築士の免許証が交付されない場合は、今回の申込をできませんか。
A2.
一級建築士免許申請書の電子ファイルを、受付システムの一級建築士免許証等添付欄に添付して申込んで下さい。
なお、講習を修了された場合の修了証の交付は、一級建築士免許証等(写)の提出後となります。
Q3.
業務の内容で、建築物の構造や規模は。
A3.
構造や規模については、特に規定されていません。(木造住宅の構造/設備の設計業務でも可)
Q4.
工作物の構造設計・設備設計については、業務経験として認められますか。
A4.
建築基準法第88条に掲げる工作物の構造設計・設備設計は認められます。
Q5.
大学や民間の研究機関等での、建築構造/建築設備の教育・研究は業務経験となりますか。
A5.
大学等や研究機関等での教育・研究は、建築構造/建築設備の設計業務等に該当する業務以外は、業務として認められません。
Q6.
官公庁での業務は実務として認められますか。
A6.
建築確認関係では、建築構造又は建築設備に関する審査業務及びその補助(構造計算適合性判定業務を含む)は認められます。
また、営繕業務については、構造又は設備に関する設計・工事監理に該当する部分は認められます。
Q7.
建築確認の審査業務は、建築主事(建築基準適合判定資格者)でないと認められませんか。
A7.
建築主事等の資格がなくても、主事等の審査の補助として行う建築構造/建築設備に関する業務は認められます。
Q8.
確認審査業務は、構造/設備に関する審査業務でなくてもよいですか。
A8.
構造/設備に関する審査に限ります。
Q9.
「業務経歴書・業務経歴証明書」の第三者証明の具体的な内容は。
A9.
原則として、現在の事務所や、業務を行った当時の事務所の管理建築士の証明となりますが、事務所内の同僚や取引先の建築士の証明も認められます。
・「業務経歴証明書」には、証明者の氏名・建築士免許種類・登録番号(二級・木造建築士でも可)・勤務先(部署名まで)・電話番号の入力が必要です。
Q10.
業務経歴の証明は、以前所属していた事務所で行った業務を、現在所属している事務所の管理建築士に証明してもらってもよいですか。
A10.
業務内容の証明が確実に可能ならば、現在所属している事務所の管理建築士等の証明でも支障ありません。
Q11.
構造設計一級建築士講習について、JSCAに所属しているがJSCA所属の他の建築士に業務を証明してもらうことは可能ですか。
A11.
可能です。
Q12.
「業務経歴書・業務経歴証明書」の様式及び入力方法は。
A12.
![]() 構造設計一級建築士講習「業務経歴書・業務経歴証明書」の入力例(PDF:228KB)
構造設計一級建築士講習「業務経歴書・業務経歴証明書」の入力例(PDF:228KB)
![]() 設備設計一級建築士講習「業務経歴書・業務経歴証明書」の入力例(PDF:246KB)
設備設計一級建築士講習「業務経歴書・業務経歴証明書」の入力例(PDF:246KB)
Q13.
構造/設備の設計のみ行っており、各業務物件の業務期間はそれぞれ1~2ヶ月しかありません。全て個別に記入する必要がありますか。
A13.
数ヶ月程度の短い期間の業務を継続的に行っていた場合には、期間中の代表的な物件を記入し、業務の内容欄にその他の物件名、建物の種類(共同住宅等)を記入して下さい。(ただし、この場合、1つの欄に記入することができる期間は1年以内とします。継続期間が1年を超える場合は、別の欄に分けて記入して下さい)
また、業務の休止期間がある場合は、この休止期間前後の継続する業務を別々の欄に分けて記入して下さい。
Q14.
業務経験の期間はいつまで計算できますか。また、希望する講習日の前日までとならないのですか。
A14.
一級建築士として構造設計/設備設計等の業務を開始した日から、構造は令和5年9月11日、設備は令和5年9月25日までとなります。
なお、建築設備士の場合は、建築設備士として設備設計等のアドバイス業務を開始した日からとなります。
Q15.
構造/設備の設計以外に並行して他の業務を行っていますが、この場合の業務期間の計算は業務の割合とするのですか。
A15.
割合を考慮する必要はありません。構造/設備の設計を行っていた期間として一般的に認められる範囲で、期間を記入して下さい。
Q16.
構造/設備の設計以外に並行して他の業務を行っている場合、業務期間は、業務割合で計算するべきではないのですか?(建築設備士等のいない設計事務所の一級建築士はほとんどこれに該当することになるのではないのですか?)
A16.
構造や規模について制限を設けていないこと、【A2】と同様に構造/建築設備技術者の幅広い業務形態を踏まえ、業務割合は考慮しないこととしております。ただし、構造又は建築設備の設計等の業務を行っている期間のみが業務経歴年数に算入可能ですのでご留意ください。
Q17.
受講資格の実務として認められる具体的な業務範囲は。
A17.
原則として、設計業務と工事監理業務となります。
Q18.
設計補助業務や工事監理の補助業務は認められますか。
A18.
平成26年度の講習から、平成25年10月以降に携われた設計補助業務や、工事監理の補助業務については、認められなくなりました。
なお、平成25年9月までに携われた設計補助業務や、工事監理の補助業務については、認められます。
※関係資料
Q19.
構造設計一級建築士講習において、構造関係の委員会の委員は業務経歴として認められますか。
A19.
現在認められている「確認審査」の関連として、
(1)「型式認定(建築基準法第37条関連)」
(2)「構造方法の認定(建築基準法第77条の56関連)」
(3)「特別評価方法認定(住宅の品質確保の促進に関する法律第58条関連)」等
に係る委員について、選任期間に建築構造の専門性を反映した継続的な認定審査を行なっている場合は、その期間が業務経歴として認められます。
また、地方公共団体が設置する耐震診断判定委員会などに属する方で、選任期間に耐震診断の検討・評価など構造に関する継続的な実務を行っている場合も同様です。
ただし、これらについては、委員会等に出席しているときのみ審査を行っている場合は、出席した委員会開催日のみが業務期間となります。
Q20.
耐震診断業務は、業務経歴として認められますか。
A20.
【5-A21】の場合を除き、「耐震診断業務」は業務経歴としては認められません。
ただし、耐震補強の設計業務や工事監理を行う場合は、認められます。
Q21.
設備設計一級建築士講習を受講するために必要な業務経歴5年以上の期間には、「建築設備士」としての業務期間は含まれますか。
A21.
「建築設備士」の場合は、一級建築士になる前の業務経歴(「建築設備士」として行う建築士へのアドバイス業務等」)も「一級建築士として5年以上設備設計に従事した」ものと同等と評価します。
Q22.
設備工事の施工管理は、業務経歴として認められますか。
A22.
設備工事に関連した「施工管理」は認められませんが、「工事監理」や「建築設備士」として行う「建築士へのアドバイス業務等」に該当する業務については認められます。
Q23.
海外での構造設計/設備設計に関する業務は、業務経歴として認められますか。
A23.
業務内容が、一級建築士(等)の資格取得後の業務経験として認められる内容であり、受講者が実施した業務内容に精通している第三者(管理建築士又は上司の建築士等)が証明していること、また、建築物が実在する場合は、認められます。
6.講習の免除措置等についての質問
Q1.
構造設計一級建築士講習の免除措置は。
A1.
(1)「一級建築士」かつ「構造計算適合性判定資格者((1)平成19~20年に構造計算適合性判定に関する講習会を受講し構造計算適合性判定員候補者名簿に掲載された者、(2)建築基準法施行規則第10条の15の3の規定に基づく者)」の方は、講義の一部及び修了考査の免除を希望することができます。該当の方は、構造設計一級建築士講習問合せダイヤル(電話050-3033-3826)まであらかじめご連絡下さい。
(2)「建築構造士」「構造専攻建築士」「APECエンジニア(建築構造技術者)」の免除措置は、みなし講習に限ったものとされており、現在の講習での免除措置はありません。
Q2.
設備設計一級建築士講習の免除措置は。
A2.
「建築設備士」は、1日の講義と半日の修了考査を受講することで、残りの講義と修了考査が免除されます。
7.講義・考査の内容等に関する質問
Q1.
講習の時間割や講習科目の詳細は。
A1.
センターホームページに掲載の「構造(設備)設計一級建築士講習受講要領」に記載してありますので、確認して下さい。
Q2.
修了考査の合格率は。
A2.
合格率は予め設定されません。合否については第三者機関を設けて判定することにしています。
Q3.
みなし講習と同じように再考査を実施しますか。
A3.
再考査はみなし講習のみの措置として実施しました。法施行後の講習では予定していません。
Q4.
免除の対象者ですが、全ての講義を聞くことは可能ですか。
A4.
講義の出欠管理の関係で、お断りしております。
Q5.
免除の対象者ですが、講習初日にテキストを貰うことは可能ですか。
A5.
受講票を持参し、講習会場に行ってもらえば可能です。一般受講者の受付時間以外に会場の担当者に申し出て下さい。
8.講習実施地に関する質問
Q1.
みなし講習では、当初予定していた7箇所以外に沖縄でも実施したと聞いたが、今回は7箇所以外で講習を実施予定はありますか。
A1.
みなし講習は、受講者対象者の数などを考慮し、全国7地区で実施する予定でしたが、沖縄県では小規模でも建築・住宅をRC造等で作る場合が多く、高い割合の建築士が構造設計一級建築士の資格を必要とすることが想定されること(数日にわたり、多くの建築士が県内に不在となってしまう)、福岡までの交通手段も限られていることなどを踏まえ、沖縄県でも講習を実施することといたしました。
今回、沖縄での講習の予定はありません。
9.その他
Q1.
過去の講習で使用したテキストは、今度の講習で使用できますか。
A1.
(1)構造設計一級建築士講習
令和5年度の講習は、令和3年度及び令和4年度と同じテキスト(2021年改訂版)を使用します。
令和2年度以前の講習で使用したテキストは、講義で使用することは可能ですが、修了考査への持込は禁止させていただきます。
(2)設備設計一級建築士講習
令和5年度の講習は、令和4年度と同じテキスト(2022年版)を使用します。
令和3年度以前の講習で使用したテキストは、講義で使用することは可能ですが、修了考査への持込は禁止させていただきます。
![]()
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Readerのダウンロードへ
Adobe Readerのダウンロードへ